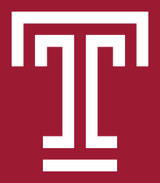 先日テンプル大学でクリストファー遥盟さんがやっている、日本音楽講座にて演奏してきました。毎年この時期に声をかけてもらっているのですが、ここでは学内が全て英語ですので、行く度にやっぱり音楽をやるには英語は必須だと痛感します。精進せねばと思いつつ、こればかりはどうも・・・。
先日テンプル大学でクリストファー遥盟さんがやっている、日本音楽講座にて演奏してきました。毎年この時期に声をかけてもらっているのですが、ここでは学内が全て英語ですので、行く度にやっぱり音楽をやるには英語は必須だと痛感します。精進せねばと思いつつ、こればかりはどうも・・・。
そしてまた外国の人に聴いて頂いていると、色々な発見もあります。日本人は古典=教養みたいなところが随分と強く、演奏者も古典をやっていると、何かアカデミックな偉いものをやっているような錯覚に囚われる事が多いのですが、そういう色眼鏡が無い分、とても素直な感想が返ってきて、自分でも改めて気付く所が色々あります。
ついこの間、ある演歌歌手が「日本の伝統文化を色濃く聞かせたい」というキャッチフレーズで 三味線弾きながらカーネギーリサイタルホールで演奏し、大変盛況だったようです。海外の人から見ると、演歌はとても日本らしい独特の文化・音楽で、且つ判り易い。大盛況もうなづけます。邦楽を演奏している方は、そんな演歌を全く違う風に捉えている。この差を自覚しない限り、邦楽はマイノリティーのまま消え去って行く運命にあるような気がするのです。
三味線弾きながらカーネギーリサイタルホールで演奏し、大変盛況だったようです。海外の人から見ると、演歌はとても日本らしい独特の文化・音楽で、且つ判り易い。大盛況もうなづけます。邦楽を演奏している方は、そんな演歌を全く違う風に捉えている。この差を自覚しない限り、邦楽はマイノリティーのまま消え去って行く運命にあるような気がするのです。
どんな仕事でもマーケティングが大切ですが、何故、演歌はどんどん市場開拓をやり、邦楽はしなかったのか?答えは簡単。邦楽の方々は音楽で食べていく必要がなかったからです。自分の満足が常に先では、小さな世界に居る方が心地良い。志向は外に向かわない。そんなドメスティックとも言える視線、姿勢をいかに早く脱却するか、そこが邦楽の最後のチャンスかもしれません。音楽は社会と共になくては。芸術音楽でもエンタテイメントでも・・・。

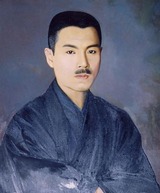
演奏家は、皆見事な演奏をしたいと思い、どうしても「上手」という事を一番に気にします。そうでなければ上達もしないのですが、宮城道雄、永田錦心等は、その演奏の見事さは勿論ですが、次世代スタンダードを作りだした感性と作品群にこそ、その魅力があるのではないでしょうか。けっして「上手」というのがポイントではではなかったはずです。
魅力的な作品があったからこそ、時代を超え、海を越えて語りつがれて行ったのだと、私は思っています。だから私も是非作品を残したいのです。色々な国の色々な音楽家が、様々な形で私の作品にぜひ挑戦してくれるようになったら嬉しいですね。

音楽は美術と比べると、常にその傍らにショウビジネスというものが寄り添っています。それは音楽の持っている性と言えるでしょう。今やマイノリティーの中のマイノリティーと化した琵琶楽、特に古典といえる作品もほとんど無い薩摩琵琶は、どこにヴィジョンを持つべきなのでしょうか。私はエンタテイメントへの志向はありませんので、カーネギーの演歌歌手のようにはいきませんが、永田、水藤、鶴田の各先人達が、次世代の琵琶楽の姿を示してくれたように、私も私なりのやり方で、次世代に視線を向けてやっていきたいと思います。その為には、どれだけ自分の身に纏わりつくものから解放されるか。そこが大事ですね。
日の出はまだ遠い?それとも近い?



