
先日、銀座シルクランドギャラリーで開かれている、日本画家の北村さゆりさんの個展「陽に タチドマル」に行ってきました。北村さんの作品は以前このブログでも紹介しましたが、威圧感が無く、知らない内に絵の前に立って、ほっとしている自分に気が付くような作品と言えば良いでしょうか。日常に溢れる情景の中に内在する、今まで気づかなかった生命が、ふわりと煌めくように立ち現れます。私はこの自然な静寂感のある世界が大好きなんです。今回は「日常と非日常の間に在る揺らぎ」を感じさせる作品たちでした。色彩はいつもながらとても自然で優しい。これまでは「水」をテーマにしたものが多かったのですが、今回は植物がテーマでしたので、特に赤系統の色が何とも語りかけてくるようで、印象に残りました。
前回書いた三浦綾子作品「青い棘」の中に「美しいものを見たい」と言いながら![aono[1]](https://biwa-shiotaka.com/wp-content/uploads/2013/02/59905fce-s.jpg) 死んでいった主人公の妻が出てきますが、人間は本来美しいものを見たいと願う生き物ではないでしょうか。だから音楽や芸術がどんな国にもあるのではないでしょうか。過剰なまでの情報と物に24時間振り回されている現代では、「美しいものを見たい」という本能が、強烈に刺激された食欲や物欲に呑み込まれ麻痺してしまっているように思います。
死んでいった主人公の妻が出てきますが、人間は本来美しいものを見たいと願う生き物ではないでしょうか。だから音楽や芸術がどんな国にもあるのではないでしょうか。過剰なまでの情報と物に24時間振り回されている現代では、「美しいものを見たい」という本能が、強烈に刺激された食欲や物欲に呑み込まれ麻痺してしまっているように思います。
地球を破壊しつくして、今度は宇宙にまで触手を伸ばして行こうという現代。加えて衛星で何でも監視され、完全に管理され切っているとも言える、この破壊と管理の社会。窮屈と感じませんか?。現代社会では、そんな閉塞感を何かに夢中に(中毒に)させることで、目を逸らすように仕向けられているかのように見えます。
私が若かりし頃見た70年代のアメリカ映画には「国境の南」という逃避的理想郷が良く出てきました。「明日に向かって撃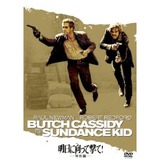 て」のブッチとサンダンスや「ゲッタウエイ」等、皆アウトローは逃れるように南を目指しました。自由の国アメリカでも、当時既に管理社会の閉塞感が在ったのでしょうね。
て」のブッチとサンダンスや「ゲッタウエイ」等、皆アウトローは逃れるように南を目指しました。自由の国アメリカでも、当時既に管理社会の閉塞感が在ったのでしょうね。
現代日本でも、「普通」といわれる枠にはまりきれない人は多いと思いますので、逃避的に「国境の南」という理想郷を求める声は大きい事でしょう。「美しいもの」に溢れ、本来の精神的理想郷たる「国境の南」は芸術の中にこそ、いや芸術の中だけに在るのかもしれません。しかしそこに逃避していて果たして豊かになるとは、私には思えない。理想郷は日々の生活の中にこそ在るべきです。芸術がただの逃避的メルヘンだったら、それは麻薬でしかない。日々の中に喜びが満ちて来なければ・・。そして世の中に多様な生き方・考え方が共存出来ていなくてはなりません。でなければ幸せな気持ちは何時まで経っても、自分にも、社会にも感じる事が出来ないと思うのです。いかがでしょう?
経済も外交も軍事も、全て社会には大事なことです。でもそれ以上に日々の暮らしが大事なのです。所構わず携帯等に見入っている姿、スマホを見ながらファーストフードを食べている日常は異常です。現代の狂気を感じずにはいられませんし、この異常さが判らないという事が、そのまま現代日本の心の貧困さを示していると思えてなりません。「これが常識」「これが普通」「こうでなければ」etc.そういう浅い画一的な考え方がまかり通るような社会は、理想郷の対極にあるように感じるのです。
目の前を盛り上げ、その場を紛らわすものばかりでいいのでしょうか・・・。こんな今だからこそ、静かに深く想いを巡らせて、命を見つめられる芸術作品に触れて欲しいと思います。そして日々を、その人なりに豊かに過ごす事が、何よりも第一と思うのです。
北村さんの作品には、生命が煌めく豊かで静寂な日々が満ちていました。



