私は日々普通に(?)生きているつもりではありますが、まあ様々な事が身の回りに起こます。誰しもそうだと思いますが、予期せぬ、というような大きいことばかりではなく、小さな驚き・喜び等々毎日色々ありますな~~。良い事、良くない事ひっくるめて日々は案外驚きに満ちています。日常のすぐ傍には様々な新しい世界の扉が口を開けて待っているかのようです。勿論扉には光もあれば、闇もありますね。

どの扉に入って行くかは、人それぞれ。扉は自分で決意を持って入るのではなく、何だかわからず、どうしようもなく、どちらかと言えば無意識で導かれるように扉に辿り着くもののような気がしています。頭で考えあぐね、思い込んでいるのは所詮「意識」の世界。自分の頭で考えた表層意識でしかない。導かれるのはそういう意識的世界ではなく、人間のこざかしい世界に存在するのではないもの、「無垢な魂」とでも言えば良いのでしょうか。そんな感じがしています。これを運命という人もいるかもしれません。
闇の扉を開ける人は、どこかでその魂が闇を求め、光の扉を開ける人は光を求めているのです。そしてこの魂というやつは、どんな知識や経験を重ねても変えようがない。最近はそんな風に思えてしかたがないのです。
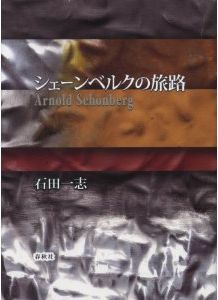
こちらは石田一志先生が最近出した、「シェーンベルクの旅路」です。先日まで小倉朗さんの「現代音楽を語る」を借りて読んでいた事もあって、石田先生から出版の連絡が来た時には、何だか自分に通じる「扉」を感じました。若かりし頃、私は現代音楽の扉を開けることで、やっと自分の魂の居場所を見つけたのです。シェーンベルクやバルトークは、作曲の石井紘美先生の所に通っている頃からよく聞きましたが、もしこういう出逢いが無かったら、きっと琵琶弾きには成っていなかったでしょう。
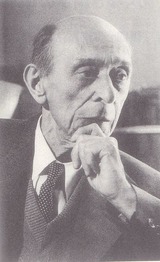
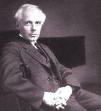
何時も書いていますが、私はポップスやエンタテイメントの音楽がどうも苦手。聞きやすいメロディー、乗りの良いリズム、聴衆を踊らせたり、泣かせたり・・・そんなエンタテイメントはなるだけ自分の音楽には持ち込みたくないのです。人間の喜怒哀楽のような現実社会の俗っぽい感情(表層意識)を超えた、もっと清純なものこそ音楽にしたいと思うのです。
「百人殺したら英雄で、一人を殺したら殺人者だ」とチャップリンは 映画の中で言っていますが、人間の善悪・感情などは、社会や国家のイデオロギーで白が黒にも赤にもなってしまう。人間はそれだけ環境に左右されて、本来の生命の煌めきなど簡単に忘れてしまう。せめて音楽ではそんな論理や目の前の感情を描くもので無く、もっとそういうものを超えた世界を描きたいものです。
映画の中で言っていますが、人間の善悪・感情などは、社会や国家のイデオロギーで白が黒にも赤にもなってしまう。人間はそれだけ環境に左右されて、本来の生命の煌めきなど簡単に忘れてしまう。せめて音楽ではそんな論理や目の前の感情を描くもので無く、もっとそういうものを超えた世界を描きたいものです。
私が琵琶を選んだのは、エンタテイメントと言う名の日常の世界を断ち切る事が出来ると感じたからこそ、琵琶を手にしたのです。そしてその清純な世界を、現代音楽の中にも感じていたのです。
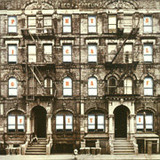 まだ小さい頃、レッドツェッペリンの「Physical Graffiti」を聞き、ビートルズみたいなポップスとはずいぶん違うことに驚きました。きっと巷に溢れている目の前の喜怒哀楽を詰め込んだ音楽のようには感じなかったのでしょう。私の感性が自然にこの音楽を選んでいたのだと思います。その後ジャズを経て、現代音楽に至ったのですが、作曲家の石井紘美先生という大きな扉に辿り着いた時も、今思うと意識ではなく、魂が導かれて行ったように感じます。だから現代音楽という扉が私に向かって開かれたのだと思っています。
まだ小さい頃、レッドツェッペリンの「Physical Graffiti」を聞き、ビートルズみたいなポップスとはずいぶん違うことに驚きました。きっと巷に溢れている目の前の喜怒哀楽を詰め込んだ音楽のようには感じなかったのでしょう。私の感性が自然にこの音楽を選んでいたのだと思います。その後ジャズを経て、現代音楽に至ったのですが、作曲家の石井紘美先生という大きな扉に辿り着いた時も、今思うと意識ではなく、魂が導かれて行ったように感じます。だから現代音楽という扉が私に向かって開かれたのだと思っています。
人生には色々な扉がすぐそばに控えるように待っているようです。穏やかな日常のすぐそばには必ず影や闇の扉があり、そこに入ってしまうと、ちょっと大変。でも影や闇が在るという事は光も在るという事。どちらか一つというのはあり得ないのです。人には光と影の両方がある、それが人の一生といえるのかもしれません。
どの扉が大事なのか。自分ではなかなか判らない。またどの扉に導かれるのかも、自分の頭ではなかなか判らない。必要な時に必要な扉が開いてくれると良いのですが・・・。魂がちゃんと呼んでくれるかな??
皆さんの傍にもきっと色々な扉が口を開けて待っていると思いますよ。
「大切なことはね、目に見えないんだよ…」
(星の王子さま S.テグジュペリ)



