友人から借りていた、世界的バイオリニストの堀米ゆず子さんのエッセイを読んでみました。とにかく世界は広い。大きい。凄いのです!!

内容はエリザベート王妃国際コンクールに挑戦する所から話が始まるのですが、どんな環境にも嬉々として立ち向かい、世界を舞台に一流の演奏家として生きて行く姿は、本当に素敵です。そして気負いなく、素直な人柄も見えてきます。
20代前半で世界の超一流の舞台に飛び出た堀米さんの姿を思うと、いかに自分が井の中の蛙であるか、ひしひしひしひしひしひしと感じました。器の違いとはこういう事なんでしょうね。邦楽特に琵琶は、己の世界に閉じこもりがちなので、私はそういう閉鎖空間を飛び越えようとあがいて来ましたが、そんな所に引っ掛かっている時点ですでに話になりません。一流は最初から見ている所が違うのです。そして一流の技術を磨き、一流の行動活動をするのです。
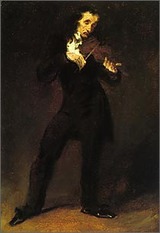
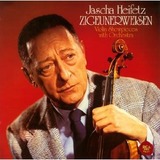
世の中何でもそうですが、ギターでもバイオリンでも、凄い技術を持った人が出ると、次の世代はもうその凄さが当たり前になって、もっと凄くなっていくものです。音楽の豊かさは勿論技術だけの問題ではないのですが、どんな分野でも技術に関してはどんどん高まって行くものなのです。
「悪魔に魂を売り渡して、その技術を手に入れた」とまで評されたパガニーニや、ハイフェッツが最高レベルの技術を示したら、次の世代はそれがもうスタンダードになって更に先を行きます。

ギターでは、エドワードヴァンヘイレンが驚異的なリズム感とテクニックでデビューしたのが79年、それ以来彼のテクニックはスタンダードになってしまいました。
 ところが琵琶は、水藤錦穣という脅威的な演奏技術を持っている人が現れたのにも関わらず、その演奏技術はどれだけ受け継がれたのだろうか?。はっきり言って誰も居なかった。唯一鶴田錦史が、独自の発展をさせたと言えるでしょう。
ところが琵琶は、水藤錦穣という脅威的な演奏技術を持っている人が現れたのにも関わらず、その演奏技術はどれだけ受け継がれたのだろうか?。はっきり言って誰も居なかった。唯一鶴田錦史が、独自の発展をさせたと言えるでしょう。
水藤錦穣という大きな目標となる、琵琶界のハイフェッツみたいな達人が居ながら・・・・。当時はきっとがんばっていた人達が居たのではないだろうかと思いますが、まことに残念で仕方がありません。少なくとも私は、音楽性は別として、水藤先生の演奏技術を追いかけたいし、超えたいと思っています。
琵琶唄に関しては、これから三味線音楽や他の洋楽器のように、語り手と琵琶の演奏を別にしていこうと思っています。両方やっていたら、アウェイで通用しない。はっきり言って、琵琶唄のうたは歌専門の歌手に比べてレベルが低いし、このままでは演奏技術も上がらない。
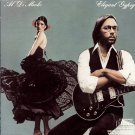
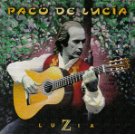
フラメンコギターのパコデルシアは、それまで閉鎖的だったフラメンコの世界を飛び出して、ジャズミュージシャン達と互角に(それ以上に)演奏し、フラメンコを一気に世界に広め、世界音楽のレベルにまで引き上げました。それもチックコリアや、アルディメオラ、ジョンマクラフリンという超のつくトップジャズメン達と挑戦的に共演したのです。77年発表のアルディメオラの2ndアルバムElegant Gypsyの中の「Mediterranean Sundance」をぜひ聞いてみてください。驚異的です。自分のフィールドでもないし、やり方も違う、全くのアウェイに於いて、今までフラメンコを聞いたことも無かった聴衆を魅了してしまう。こんな凄い事が世界では次々に起こっているのです。
どのように音楽を捉えてもいいし、琵琶をどう弾いても良いと思います。そして私ごときが何をやっても堀米さんの100分の一いや100000分の一の成果も出せないでしょう。でも目指さずにはいられないのです。たとえそれが井の中の蛙のあがきであっても・・・。
エッセイを読んでいて、一気にファンになってしまいました。是非生演奏を聴きたいですね。ガルネリも早く戻ってくるといいですね。



