毎年8月、琵琶樂人倶楽部ではSPレコードコンサートをやっていまして、往年の琵琶名人を蓄音器の名器ヴィクトローラクレデンザで聴いて頂いてます。
これがヴィオロンのクレデンザ。実は最近ヴィオロンでは、この手回し式のクレデンザに加え、電動式のものもコレクションに加えました。昔は家一軒分位の値段がしたというクレデンザ。今でも現存するものはわずかです。
毎年このSPコンサートの為に、ヴィオロンのマスターとSPレコード探しに神保町に行くのが、毎年のお楽しみ。
SPレコードは確かに現代で言う所のノイズは多いのですが、その音の臨場感あふれる音に圧倒されます。私達が普段聴いている「いい音」がいかに空々しい人工物であるか、実感してしまうのです。SPは昭和37年まで生産されていましたので、まだほんの50年前。明治11年に最初の実験録音が東大であり、明治36年に国内で発売されているので、ちょうど薩摩琵琶、筑前琵琶の歴史と同じ位と言えます。![image005[1]](https://biwa-shiotaka.com/wp-content/uploads/2012/07/9a0e7625-s.jpg) 録音方法も、初期はラッパに向かって演奏していたので、録音レベルが小さいですが、昭和2年からマイクロフォン録音(マニアの間では電気録音という)が始まりました。←のレーベル面には「電気吹込」の文字が見えます。こういうのを探すのが面白いんですよ。
録音方法も、初期はラッパに向かって演奏していたので、録音レベルが小さいですが、昭和2年からマイクロフォン録音(マニアの間では電気録音という)が始まりました。←のレーベル面には「電気吹込」の文字が見えます。こういうのを探すのが面白いんですよ。
テクノロジーの進歩は人間の退化、とよく言われますが、年を経ることに確かにそう思います。当時はレコーディングの現場も、一発録音しかない、という凄い緊張感だった事と思いますが、今それが出来る実力を兼ね備えた演奏家は、どんどん少なくなっているように思います。
![image016[2]](https://biwa-shiotaka.com/wp-content/uploads/2012/07/3edb45e8-s.jpg)
![image016[1]](https://biwa-shiotaka.com/wp-content/uploads/2012/07/e593511b-s.jpg)
とにかくSPレコードというのは今やお宝。以前は良く中古レコード屋でLPをあさっていましたが、この現代でSPを探すというのはとにかくマニアックで、なかなか面白いのです。何だか未知の世界を覗くようでわくわくしますね。5年間やっていますが止められません。現代人はいつも一定の情報に囲まれているせいか、ネットに出てこないものには興味を示さない人も多いですが、ネットに出ている情報なんざほんのわずか。かけらしかない。足で探さないとお宝には巡り逢えないのです。
驚くのは筑前琵琶。ピアノとデュオでやっているものもいくつもあって、なかなか華やかで進歩的で、皆さん琵琶の音程も歌の音程も現代の演奏家よりとても正確。技術に関しては水藤錦穣さんなどを抜かせば、筑前の方が上を行っている感じがします。今、琵琶で弾法も歌もピアノと一緒にやれるような人は数えるほどしかいないのではないでしょうか。今の琵琶界の衰退が見えてきて、情けないやら悲しいやら・・・・。

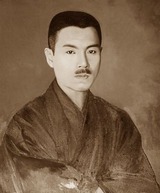

現代社会はネットでもメディアでも情報がいっぱい溢れているようですが、そういう風に見えるだけで、実はほんの一面でしかないのです。皆判っていながらそこに一日中振り回されて、囚われている。SPレコードを通してそんな世の中がよく見えてきます。
さあ、そろそろリアルな真実の世界に飛び出してみませんか。目が覚めますよ。




