先日、琵琶樂人倶楽部が第50回目を迎えました。足かけ5年、古澤錦城さんと毎月レジュメを書いたり、演奏したり、話をしたりして開催して来た軌跡を今、感じています。



過去の軌跡は以下を参照ください。
http://biwa-shiotaka.com/?page_id=46
毎回テーマを決めて、それに沿った話、レジュメ、演奏を追われるようにやっていますので、自分でも良い勉強の場となっています。先日の50回目は定番のテーマで、「平安期の楽琵琶について」を新ネタ入りで話をさせて頂きました。
琵琶(特に薩摩琵琶)の世界は音楽学という分野が著しく遅れています。演奏家の琵琶に対する認識も、他のジャンルに比べ、いつまで経っても成熟しません。明治に出来た尺八都山流は、自分たちの曲をけっして古典とは言わないし、現行の雅楽でも「近代雅楽」とはっきり言っているのに対し、琵琶では昭和になって出来たものや戦後数十年しか経っていないものでも、古典と言ってはばかりません。さすがにこれは情けない。現代音楽の祖といわれているバルトーク・シェーンベルクでも19世紀の生まれですよ!!
こういう姿勢が今の琵琶のレベルをそのまま表しています。
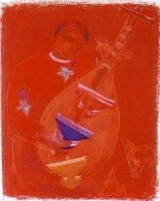
 こんな中で、琵琶樂人倶楽部ではその歴史を辿り、明確にレクチャーすることで、先ずは歴史認識をしっかりと正し、それぞれの時代の琵琶楽の魅力を紹介し、そこから次世代への可能性を探っていこう、という主旨で始まったのです。場所を提供してくれている名曲喫茶ヴィオロンのマスターにはとにかく感謝しかありません
こんな中で、琵琶樂人倶楽部ではその歴史を辿り、明確にレクチャーすることで、先ずは歴史認識をしっかりと正し、それぞれの時代の琵琶楽の魅力を紹介し、そこから次世代への可能性を探っていこう、という主旨で始まったのです。場所を提供してくれている名曲喫茶ヴィオロンのマスターにはとにかく感謝しかありません
小澤征爾さんの本を読んだり、Metのオペラを見ても思いましたが、最高峰といわれる人達は、クラシックという歴史あるものをやっていても、それを最先端の表現として舞台にかける。古典をしっかりと勉強しても、古典という権威や形に寄りかからない。世界の大舞台で、最高レベルのものをやっているという意識はやっぱり凄いものを生み出します。
他の方は色々な考え方があると思いますし、どういう考えを持っていてもかまわないのですが、私の個人的な想いとしては、琵琶楽が日本から世界に発信するような音楽でありたいと思っています。世界の人が琵琶を聴いて感激するようなものでありたい。日本の、それも一部の人が喜んでいる、東洋の一民俗芸能ではなく、たとえ小さな舞台でも、世界に通用する芸術音楽でありたい。単なるヒットソングではなく、ドビュッシーや武満やマイルスやコルトレーンやジェフベックやクリムゾンと同じステージに居たい。その為にも琵琶楽の歴史認識やこれまでの琵琶楽を勉強することはとても大事なのです。そしてその脈々と伝えられてきたものを、どのように現代や次世代に向けて表現して行くか、今それが問われていると思います。

琵琶樂人倶楽部の活動を通して私が感じたことは、このような事です。Metの舞台もバロックをやろうが現代ものをやろうが、常に最新の演出、最高の技術、最上級のキャストで現代最高峰の舞台を作り上げて行く。琵琶楽もその志でありたいのです。
小さな己の世界に閉じこもっていては始まらない。目の前の事を追いかけているだけでは、いつまで経っても日々の食い扶持にありついているだけです。その辺のことを常に自分に言い聞かせて、もっとその先の世界に視線を、感性を向けて演奏していきたいのです。
琵琶樂人倶楽部を始めてから、シルクロードツアーが実現し、樂琵琶でも活動が広がり、クラシックの音楽家達とも共演がはじまりました。歩みは遅いですが、私にとっては皆素晴らしい事です。小さな会ではあっても、ここからどんどんと大きな世界へと目を向けて、羽ばたいていきたいものです。
今後の琵琶樂人倶楽部にもご期待ください。



