前回のブログで高橋竹山のことを書いたら、結構色々な方からメッセージを頂きました。皆さんやっぱり竹山には関心が高いんですね。
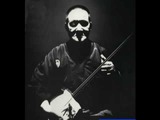
私が竹山贔屓なのには、何かしら自分と共通するところを感じるからです。もちろん私は竹山のような、壮絶な生き方はしていませんし、竹山から比べれば甘っちょろいもいいところなのですが、私も琵琶を始めた頃は、関西のギャラリーやサロン、古本屋さんや、ブティック等々、ライブが出来そうな所を片っ端から回り、月に10本15本と一人で小さなライブをやっていました。
流派には形だけ居ましたが、曲もオリジナルでやっていましたし、弾き方も歌い方も自分で作り出していったので、何となく竹山と似たものを勝手に感じてしまうんです。
私ははこんな具合で活動を開始したので、肩書きの付くような所や、大きな劇場には当然のように無縁で、やれ何とか先生だの、何とか流だの、何とか賞だのというような、いわゆる「邦楽人」とは未だにあまり付き合いがありません。ライブから始めた仲間でも、ある程度の年齢になると受賞歴やら名取やらと肩書き、看板を挙げてそれなりの体裁を繕って先生になりたがる人も多いですが、私はそういう人達とは基本的にタイプが違うのです。
前にもちょっと書きましたが、竹山と同時代には木田林松栄という名人も居ましたが、木田と竹山は、性格も演奏も、何から何まで全く正反対でした。木田はばっちりと組織を作り、弟子をいつも何人も引き連れ、何百万もする三味線を見せびらかして自慢して・・・。まあそれだけ親分肌で面倒見の良い人だったのでしょう。琵琶でしたら、鶴田先生がよく似ていますね。しかし私は、芸はともかく、そういう俗物的な所が、どうも肌に合わないのです。
大きな音で派手なはったりをかまして、ショウビジネスとして、民謡を組織化してやっていた木田と、晩年まで温泉場を回ったりして、あくまで己の音とスタイルを貫いた竹山。良くも悪くもこの差がすべて二人の音色に出ているように思います。

これは竹山の像だそうですが、この表情を見ていると、彼がどれだけ愛されたか判りますね。
そして竹山の素晴らしいところは、最初に歌と三味線を習って、その後三味線に専念したことです。旅の途中に喉を痛めてしまってから、歌うのをやめたそうですが、歌を自分で歌っていた経験があったからこそ、あの絶妙な歌付けが出来、更に三味線に専念していたからこそ、あれだけの歌付け、そして曲弾きが出来たと言えると思います。歌も三味線も両方追いかけていたら無理だったでしょう。
薩摩琵琶や筑前琵琶は常に弾き語りでやりますが、やはり両方をやるとどちらかがおろそかになるものです。どちらかに専念していたら、名人と言われる歌い手も、弾き手ももっと世に出たかもしれない、と思いますね。
永田錦心は新たな感性で、次世代スタンダードとも言えるスタイルを築いたという点で素晴らしい功績がありましたが、弾く方は大したことは出来なかった。雨宮薫水や榎本芝水も、歌の技巧はそれなりにあったけれども、弾く方は通り一遍の平凡なものでしかなかった。今、冷静に見て、琵琶の世界で両方を評価されるのは、水藤錦穣・鶴田錦史くらいだと思います。これからはどうなって行くんでしょうね・・・・。

竹山は弾く事に専念したことで、あの即興曲「岩木」も生まれ、新たな時代を私たちに見せる事が出来たのでしょう。またショウビジネスに寄りかからず、お金を儲けることや、有名ななることにも頓着無かったからこそ、あのスタイルが築けたことと思います。
音楽をやっていれば、誰でも有名にもなりたいし、売れたいと思うもの。竹山にももちろんあったでしょう。でも竹山はそれよりも自分の人生をまっとうに生きたいという気持ちの方が強かった事と思います。上昇志向や自己顕示欲が人一倍強く、ショウビジネスとして活動していった木田とは、その人生も大きく違いました。
自分の音をどこまでも求め、己の分を知り、まっとうに活動し、生きて行く。これらは竹山を通して改めて感じたことであり、私の指針です。

蕩々と広がる雲のように、ゆったりと確実に己の生を歩みたいですね。



