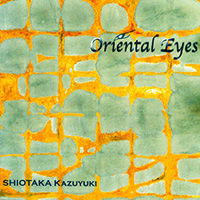東洋大学での特別授業、豊田市「てぃいだカンカン」での文弥人形との共演、そして定例の琵琶樂人倶楽部と立て続けにやってまいりました。
東洋大学はこのところ御縁のあるところなのですが、今回は学生に向けての授業という事で、琵琶の歴史に日本の歴史を搦めて、ざっとですが説明させてもらいました。学生達は皆とてもフレッシュで、中にはジャズ研に入っている生徒もいて、何かと話も盛り上がりました。
豊田の会場は小さなスペースではありましたが、二回公演で二回とも満席。お客様の反応も結構なものがありました。猿八座とは初めての共演でしたが、この形には可能性を感じますね。人形の表情の豊かな事!。人間の役者よりもずっと身に迫るようなリアルさで語りかけてくれます。また是非共演してみたいですね。
先日の京都もそうでしたが、最近何か風のようなものを感じます。それもとても新鮮で新しいさわやかな風を感じるのです。
最近は目まぐるしいほどに仕事に追われていますが、ほとんど弾き語りはやっていません。思う形になってきたことで、妙なストレスも無くなり、本来の水を得て、泳ぎ回っているという気がします。琵琶で演奏活動を始め20年、ようやく一巡したのか、1stアルバムの「琵琶に可能性しか見ていなかった」頃と同じような風が自分を取り巻いている、そんな感じがしているのです。やはり私の音楽は器楽に極まるのでしょう。
自分で弾き語ると、どうしたって声に意識が行ってしまうし、声で表現しようとしてしまう。琵琶奏者は琵琶で表現出来てナンボ。声に寄りかかってはいけません。歌で表現したのなら、歌手として歌に専念すべきです。中途半端では魅力ある音楽は創れないので、やはり私は器楽に重きを置いてゆくこのやり方が合っているようです。
若き日 京都清流亭にて
何しろ琵琶のこの音色をもっと聴かせたいですね。声は素晴らしい歌手や語り手が沢山いるので、私は琵琶に専念して、この妙なる音でリスナーの心を揺さぶる位の演奏家になりたいです。私が20年舞台活動して来て思うことは、リスナーの方も演奏家も、「珍しい楽器」というところで終わってしまっているという事。つまり音楽を聴いていないのです。
琵琶という楽器が珍しい飛び道具のようなものではなく、素晴らしい音色を湛えた素晴らしい楽器であり、且つそこから魅力ある、人を惹き付けてやまない、そんな楽器であって欲しい。それをやるのが私の仕事なのです。その為にはリスナーが最初に琵琶に対して漠然と抱くイメージの数段上を行くような音楽を演奏する事。決して上手やお見事という、旧い価値観で演奏せず、またリスナーのイメージに媚びるような予定調和の演奏をしない事。これに尽きます。先ずはなんと行っても魅力的な曲でなければ人は聴いてくれません。
私はJpopはあまり聞きませんが、スガシカオさんや中村中さんの曲は結構好きなんです。何といっても歌詞が素晴らしい。あの声と、他には無い独特のメロディーで歌われると、もう曲が流れ出したとたんに、彼らの描く世界に誘われて、すっと世界に入ってしまうのです。
私の音楽性とは全く違うのですが、琵琶でもあれくらい人を惹きつける曲が出来ないものかな~~と何時も思います。大声出して、こぶし回して、旧態然とした~今の世の中に到底理解されないような~価値観をうたっている音楽をやっているのは、私には全く理解ができません。
舞台「良寛」にて
琵琶と声は中世以降密接な関わりがあります。私は器楽を第一に追及しますが、同時に声に関しても、今迄の琵琶歌のあり方を根底から覆して、琵琶と声との新たな関係を創り上げたいと思っています。
実はこれから声を使った四季を寿ぐ作品を、とある方と組んで作曲する予定なのですが、歌をメインにするのではなく、器楽の中に声が入るという形になります。あくまで歌ではなく、楽曲として琵琶の音色が生きるものにしようと思っています。感性も内容も普遍的に幅広い世代に通じるものを専門家にお願いしています。
琵琶の歴史をみれば確かに言葉と共に在ったのですから、言葉を軽んじることはできません。しかし言葉に寄りかかり、魅力的な音色が出せないのでは琵琶を弾く意味がありません。こちらは来年の秋ごろをめどにお披露目をしようと思っています。乞うご期待!。
この風が私には目に見えるような気がするのです。20年前も風を感じましたが、20年経ってまた吹き来るこの風は、もう少し優しく、且つ揺るぎなく、聴く人を包み込んで豊かさを運んでくれるように感じます。この風は私が待ち望んでいた風であり、また自分自身の身体に元々吹き渡っていた風のような気がします。この色というのか、温度というのか、匂いというのか、表現は難しいですが、この風を身に感じ、今私の視界に見えているという事は、とても素敵な事なんだろうと思うのです。