この所ぐっと涼しくなって体が楽になりました。この秋は有り難いことに地方公演が毎月入っています。昨年の秋も随分とお仕事を頂きましたが、こんな時代に本当に感謝しかないですね。今週は11日土曜日に「人形町楽琵会」もあるので気合も漲ってきました。公演が是非まっとうに上演できるよう祈るばかりです。
さて、今日は久しぶりに少しばかり継琵琶、そしてメンテのお話など。
私は国内でしたら九州でも四国でも山陰でも、時間さえ許されるのであれば延々陸路で行くことが多いのですが、どうしても飛行機で行かなければならないこともありますので、秋の演奏会シーズンは、分解型の継琵琶が活躍します。この継琵琶は14・5年前に作ってもらった塩高モデル中型(左写真)なのですが、それを右写真のようにネックの付け根から、ばさりと切って分解型にしてもらいました。元々かなり良く鳴る琵琶で、5thCD「沙羅双樹Ⅱ」のレコーディングの時に使ったものなので、ツアーにもよく持って行ったものでした。しばらくしてそのまま使っていたのですが、当時就いていた師匠の勧めで漆を表面に塗ったところ、これがどうも良くなかったのか、今一つ鳴りが小さくなってしまいました。そこで分解型にする際には、一度バラバラにして、表だけでなく、内側に少し入っていた漆も全部剥いでもらって、それから分解型に改造してもらいました。改造してもらってもう丸4年経ちます。
上のURLは分解型にしてもらった時の記事です。琵琶職人の石田克佳さんも一体型の琵琶を切って分解型にするのは初めてだったようで、大分苦労されたようです。無理を聞いて頂きました。
継琵琶に改造された当初は、継ぎ目の所に大きなブロックが入っているせいか、どうにも鳴りが元のように戻らず、サワリや絃をはじめ細部を、さんざんいじり倒していました。特に糸口はこの継琵琶から貝プレート仕様にしたので、最初は本当に試行錯誤状態でしたが、今では結構いい感じで鳴るようになり、ちょっとしたリハーサルにも持って行くようになりました。
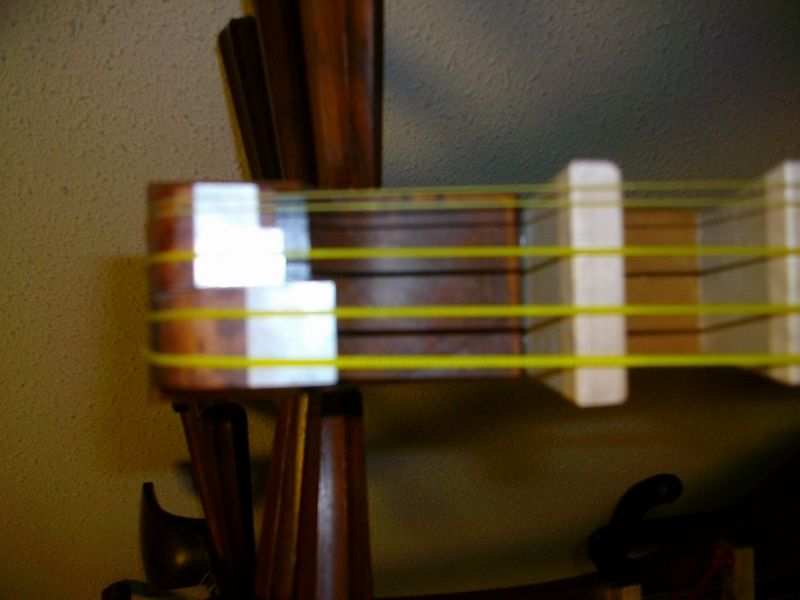 貝プレートの糸口は土台を壊すほどにいじった末、一度土台ごと交換してもらって、やっとセッティングが決まりました。今では4面の塩高モデルが全てこの貝プレートになっています。もう当分海外公演はないと思いますが、とにかく象牙のパーツは空港でいつ没収されるか判らないので、塩高モデルの4面は貝プレートだけでなく、以下の写真のように全て完全な象牙レス仕様になっています。下の写真を拡大してみてください。以前の記事にも書ききましたが、月マークは、大型が黒檀、中型が金属と貝。腹板の横線は黒檀。覆手の部分は大型が黒檀、中型が貝になっています。
貝プレートの糸口は土台を壊すほどにいじった末、一度土台ごと交換してもらって、やっとセッティングが決まりました。今では4面の塩高モデルが全てこの貝プレートになっています。もう当分海外公演はないと思いますが、とにかく象牙のパーツは空港でいつ没収されるか判らないので、塩高モデルの4面は貝プレートだけでなく、以下の写真のように全て完全な象牙レス仕様になっています。下の写真を拡大してみてください。以前の記事にも書ききましたが、月マークは、大型が黒檀、中型が金属と貝。腹板の横線は黒檀。覆手の部分は大型が黒檀、中型が貝になっています。

これからの琵琶人には、大声張り上げてご満悦のようなレベルを早く卒業して、是非楽器そのものにもっと興味を持って欲しいし、舞台に立つような方は、サワリや撥先、絃に気を遣って欲しいものです。時々楽器に対し「愛情欠乏症」とも思えるような、酷い状態の琵琶を弾いている人を見かけますが、よくあれで平気だなと、逆に感心します。最初にあの音を聴いた人は、琵琶にどんな印象を持つんでしょうね・・。琵琶を弾いて歌う歌手でありたいのか、琵琶奏者でありたいのか人それぞれだと思いますが、いずれにしろ、琵琶を珍しい飛び道具のように扱ってほしくないですね。愛情をたっぷり注いで、その琵琶が最適な音で鳴るように奏でていただきたいものです。
笛:福原道子さん 福原百桂さんと、寶先生作曲の「花の寺」演奏中
上記の写真は大分能楽堂での長唄笛方 寶山左衛門先生追悼の会の時のものです。実は私の舞台デビューが寶先生の舞台でした。まだ30代の頃で四谷の紀尾井ホールにて、寶先生作曲の笛と琵琶の為の「花の寺」を演奏しました。その公演では、当時就いていたT師匠も他の曲で出演したのですが、会場に居た知り合いの笛奏者の方から、私の演奏を聴いて「音色が師匠とは全然違う。まだまだだね」と言われたのです。原因は勿論私の技術の無さですが、中でもサワリの詰めが甘かったからです。高音の余韻が無く、全体のサスティーンもバラバラだったのでした。それは当然そのまま私の演奏の質に直結します。厳しい評を頂いてしまったという事です。小手先の技に執心して、肝心かなめの音色が出来ていない自分を大いに恥じ、また自分のスタイルが思い入れだけで空回りしていて、全然出来上がっていないという事も痛感しました。師匠のメンテの行き届いた琵琶を改めて聴いて、これが一流の壁かと実感しました。悔しかったあの気持ちは今でも忘れないですね。それはプロとして舞台に立って行く為の貴重な体験でした。
歌手なら自分の声は命です。その命を守るためにありとあらゆる努力をしています。同じように琵琶を弾く人は琵琶の音色が命なのです。だから常にメンテをして整えてあげることは、凄い事でもなんでもない。琵琶弾きとして生きてゆく上での当たり前の事なのです。ヴァイオリニストもギタリストも皆さん、自分の楽器には目いっぱいの愛情を注いでいます。
私もこの所いっちょまえに、少しばかり琵琶を教えるようになりましたので、そろそろこれらのメンテナンスのやり方を生徒達に教えようかと思っています。次世代の楽器として継琵琶にも慣れて行って欲しいですし、自分の音色と音楽をしっかり掴み取って、自分独自の琵琶樂を築き上げて行って欲しいと思います。その為には日々のメンテナンスがとても大事なのです。今まで私がこの25年程培ってきたノウハウをしっかりと教えてあげたいですね。
この秋も継琵琶が活躍しそうです。琵琶樂がマニアの為に存在するのではなく、もっと今を生きる人々に寄り添って、様々なスタイルが支持されて、世の中に鳴り響く事を願っています。








