
今年は鎌倉などでは、あまり綺麗な紅葉が見られないと聞いていましたが、先日、九段下の近くに用事で行った時、北の丸公園を通り抜けたら、実に素晴らしい紅葉に出会いました。
深まり行く秋というものは何とも風情がありますね。春も勿論ですが、こうして季節が移り行く様は、本当に詩情を掻き立てられます。やはり日本の音楽はどこまでも自然と共に在り、日本人もまた自然の一部として生きているんだな~~と毎年感じる事が出来ますな。この感性が和歌を生み、平安文化を創り上げ、中世へと引き継がれていったんでしょうね。能や茶道、華道など現代の日本の文化の根幹となっているものは、皆この感性の上に成り立っていると思わずには入られません。古の歌人も紅葉を愛で、和歌を詠み、心を豊かにしたんでしょう。この感性が現代迄受け継がれ続いているということに、ロマンを感じますね。
私は一年を通して、大体毎週どこかで演奏しているのが常なのですが、時々ふと演奏会が一週間~十日無いという時が数ヶ月に一度位あります。こういう時が自分にはとても必要で、この余裕があるからこそ、紅葉や春の花や空や雲など、自然に接して感性が広がるのです。常に追われているばかりでは愛でるどころか、気がつきすらしませんからね・・・。
楽器も同じで、愛でてあげるくらいの時間がないと、こちらの感性には答えてくれません。私の楽器が常にベストコンディションでいられるのは、ゆっくりメンテしてあげる時間があるからです。楽器は演奏家にとって命ですから、たっぷり愛情も手をかけてあげないとね!!!。
 これは石田琵琶店の3代目の作品。私の琵琶の製作やメンテナンスをやってくれている石田克佳さんのおじいちゃんの作。大正時代との事です
これは石田琵琶店の3代目の作品。私の琵琶の製作やメンテナンスをやってくれている石田克佳さんのおじいちゃんの作。大正時代との事です
先週も珍しく演奏会が十日間程無く、時間がありましたので、早速楽器の調整を片っ端からやっていて、サワリはもちろんの事、柱をはずして音程や高さの調整をしたり、糸巻きの密着具合を確かめたりしてたっぷり「愛でて」あげました。今回は特に中型と標準サイズの調整をしましたが、写真左の標準サイズが、結構良い感じに仕上がりましたよ。ビュンビュン鳴るようになりました。
その他はレパートリーの譜面も総点検して、楽譜の書き直しにも時間をかけます。普段やっていていると、「ここのタッチを変えてみようかな」「ここのアレンジ変えてみようかな」という小さなアイデアが結構溜まって行くので、そういう小ネタを片っ端から実践してブラッシュアップしているという訳です。
新作としては、最近は笛と樂琵琶の小品1曲と、短い樂琵琶独奏曲を先月仕上げました。この独奏曲はもう少し発展させて、今までのオリエンタルムードではない、幻想的な現代作品に今後仕上げて行くつもりです。他にも幾つかアイデアがあるので、それらを具体化して、来年末にはまたアルバムを録音したいと思っています。今後はCDの制作をやめて、配信のみになって行くと思いますが、どんどん創って行きたいと思っています。特に薩摩琵琶の独奏や他の楽器とのデュオ曲などをもう少し創りたいのです。
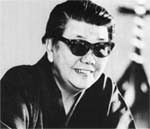
来年の活動についても色々と考えています。戦略というほどの大げさなものではないのですが、思う形で活動を進めて行くには、計画を立てるのはとても重要。演奏会ごとに、求められる曲も違えば、共演者も様々。しかしどんな演奏会であっても、全てに於いて私の音楽が鳴り響かなくては、私がやっている意味がありません。
私は日本橋富沢町樂琵会と琵琶樂人倶楽部という二つの定例会を主催しているのですが、両方とも1年間のスケジュールを前年の10月までには決めます(出演者も内容も)。琵琶樂人倶楽部は年に12回、日本橋富沢町樂琵会は年に5回の計17回の演奏会を1年以上前に決定しているのです。もちろんゲストの方にも連絡を取って承諾を頂き、前年の11月には次の年の一年間のスケジュールが入ったチラシを配り始めます。
スケジュールでもコンテンツでも、先ず自分でやれることを把握して、何をどうやれば自分の音楽が伝わるのか、じっくり考える事が必要です。かの鶴田錦史師は、「才能なんて関係無い。自分の全てが武器になる位でないと」と言ったそうです。少しばかり上手だとか、才能があるとかそんなことではなく、その人の顔も姿も下手も上手いも、何でも丸ごとがその人の武器、つまり自分の全てを魅力として輝かせることが出来るかどうかということだそうです。さすが鶴田先生らしい名言だと思います。
活動を続けていると、どうしても目の前の事に囚われて、ただ一生懸命になるだけで、全体が見えなくなることがあるものです。一所懸命やっている自分に酔っているとも言えるでしょう。日本人は特に「上手」や「お見事」というのが大好きで、誰かのそっくりに歌えるとか、弾けるとか、そんなところを賞賛する傾向がジャンル問わず多いので、おだてられてうっかりそういう所を向いてしまうと、もう自分の音楽は響かない。先日もYoutubeで、往年のポップス歌手そっくりに歌う方が話題でしたが、大変上手だとは思うものの、物真似芸人にしか見えませんでした。それを楽しんでいる分には結構だと思いますが、物まね芸では世界は認めてくれないのです。世界とそのまま繋がっている現代では、視野の狭さは命取りです。プロではやって行けない。
私のような規模の小さい音楽でさえ、ネット配信を通じて海外から問い合わせが来るのが、現代という時代です。自分の発した音楽はそのまま世界を駆け巡るのです。
貴方は誰かのそっくりさんや二代目になりたいですか?。それとも他の誰でもない貴方の音楽を世界に響かせたいですか・・・?。
季節が移り変わるように、私の活動も刻一刻と世の中と共に移り変わって行きます。事にここ10年程のSNSの発展やネット配信によって、完全に世界に向かって発表して行くという意識に成らざるをえない状況になってきましたし、Youtube Musicなどの新しいサービスもどんどん始まり、その状況は日々更に発展し続けています。こういう世の中で活動しているという意識を持てるかどうか、そこがポイントですね。
私の琵琶楽に対する基本のスローガンでもある「器楽としての琵琶」という部分も、自分の中で大分徹底してきましたので、自分の作品をどんなプログラムで聴かせ、舞台全体を張って行くのか。そしてどんな形と方向で活動を展開するか、年を追うごとに、その器とセンスを問われているように感じます。
今月も色々と演奏会が続いて、13日には前回書いたように、日本橋富沢町樂琵会で津村禮次郎先生との共演もありますので、あまりゆっくりは出来ませんが、年末には毎年演奏会がなくなるので、じっくりと腰を据えて、季節を楽しみながら、これからの自分について考えて行きたいものです。
豊かな音楽を創りたいですね。
 これは石田琵琶店の3代目の作品。私の琵琶の製作やメンテナンスをやってくれている石田克佳さんのおじいちゃんの作。大正時代との事です
これは石田琵琶店の3代目の作品。私の琵琶の製作やメンテナンスをやってくれている石田克佳さんのおじいちゃんの作。大正時代との事です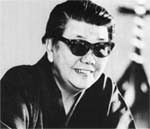 来年の活動についても色々と考えています。戦略というほどの大げさなものではないのですが、思う形で活動を進めて行くには、計画を立てるのはとても重要。演奏会ごとに、求められる曲も違えば、共演者も様々。しかしどんな演奏会であっても、全てに於いて私の音楽が鳴り響かなくては、私がやっている意味がありません。
来年の活動についても色々と考えています。戦略というほどの大げさなものではないのですが、思う形で活動を進めて行くには、計画を立てるのはとても重要。演奏会ごとに、求められる曲も違えば、共演者も様々。しかしどんな演奏会であっても、全てに於いて私の音楽が鳴り響かなくては、私がやっている意味がありません。






