暑い日々が増えて来ましたね。私は自分自身が暑さに弱いのに加え、琵琶も湿気が大敵なので、どうもこれからの季節は苦手です。
最近は色んな方の琵琶の手入れをする機会があり、色々と勉強になります。皆それぞれに好みがあり、スタイルがあり、この多様さが琵琶の魅力になっているんだなと実感します。一人一人声も顔も違うように、琵琶の音も色々あるのだと思います。もっとそれが音楽として個性的な琵琶樂が飛び出して行って欲しいですね。

教えている生徒のものは、いつもサワリ調整のやり方を見せ教えてながら調整してあげるのですが、是非自分で出来るようになって欲しいものです。生徒の中に最近分解型琵琶を手に入れた人が居て、そのサワリを診てあげたら、とても良い感じで鳴り出して気持ち良かったですね。喜んでましたよ。何だか私も嬉しくなってしまいました。彼は弾き語りスタイルを中心にして色んな場所で演奏しているので、あの分解型は、これからきっと彼の良きパートナーとなって行くんでしょうね。
ギターなんかも同じですが、新しい琵琶は手に届いてから、細部のセッティングを自分なりに調整してあげないと本来の音が出て来ません。先ず絃を自分に合うものに替え、その上でサワリの調整を細やかにしてあげて、そこからがスタートです。コツコツと自分なりの工夫をしながら育てて行ってこそ唯一無二のパートナーになって行くのです。最初の調整をおろそかにすると、いつまで経っても楽器のポテンシャルも引き出せないし、パートナーにもなってくれません。
時々知り合いの琵琶も頼まれて調整するのですが、声を使う人には長いサスティンや響き過ぎるサワリは歌にとって扱いにくくなってしまいますので、その辺も考えてやることが必要です。先日も筑前琵琶のサワリ調整をしたのですが、一の糸をいつもの調子でばっちり鳴るように調整したら、さすがに鳴り過ぎて歌いにくいという事でサワリと鳴りを押さえるような調整をしました。そうしたら全体がしっとりとした弾き歌いにちょうど良い感じでバランスが取れて響いてくれました。サワリの調整をする時には「これはどう?、もうちょっと渋くする?」なんて調子で話しをして、相手の好みを確かめながらやるのですが、人によって求めるサワリが様々で、そういう話がなかなか楽しいのです。何事も正解が一つしかなく、ゴールが決まっているようなものは面白くありません。多様な琵琶のスタイルに常に触れていられるのは幸せであり、良い勉強になりますね。
それにしてもサワリの調整一つでこれだけ変化に幅がある楽器というのも珍しい。ギターやピアノも勿論調整で大きく変わりますが、琵琶程変わる楽器は他に見た事がありません。
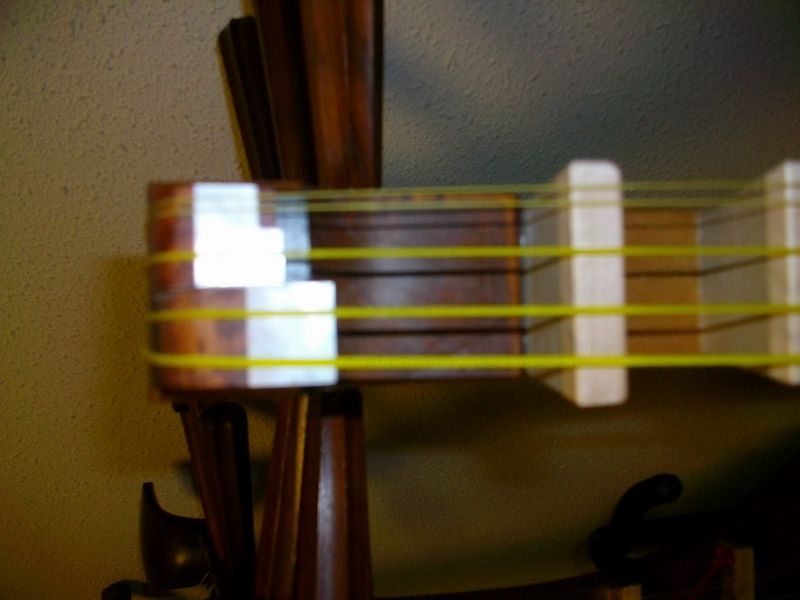
特に糸口のサワリ調整は、全く別物になるので一番気を遣います。多分このブログを見ている琵琶人も同じように感じている方も居るでしょう。自分で調節できるようになると自分だけのサウンドが出せますよ。
また貝プレートの糸口になじめない方も多いかと思います。私も最初はちょっと音色がどうなるか心配だったのですが、約8年程舞台やレコーディングで使い続けた実感として、象牙の糸口も貝プレートも、その音色は象牙のものと変わらないと感じています。全く心配なく使えてます。しかも貝プレートは削り過ぎたらプレートを交換するだけでコストも手間もかかりませんし、土台の木部を削らない限り、とてもメンテナンス性が良いのです。
これからの時代を考えれば象牙の使用は世界的にも無理がありますので、早い時期に貝プレートに替えて本当に良かったと思っています。少し前に象牙の糸口のままアメリカに琵琶を持って行って没収された方が居ましたが、これからの琵琶人には是非貝プレートをお勧めします。勿論サワリの調整が自分で出来るというのが前提ですが。
材料はどんどん変わります。どんな楽器でも素材は世の変化と共に変わって行きます。素材自体が枯渇する事もあるし、時代が求める音色が変化して行く事もあります。しかし皆それぞれの時代の魅力的な音を目指して、素晴らしい音楽を創り上げているのです。ピアノの鍵盤もドラムのヘッドも弦楽器の絃も、どんどん変化しながらも素晴らしい音を奏でる為に、時代に見合う演奏テクニックを演奏家が開発し、新しい音楽を創造し、それぞれの時代の音楽を創り出しているのです。
 桑の土台の上に黒檀、その上にスネークウッド、そして貝プレートという構造
桑の土台の上に黒檀、その上にスネークウッド、そして貝プレートという構造
先日の琵琶樂人倶楽部は琵琶職人の石田克佳さんを招いて「琵琶トーク」をしたのですが、お客様から高い倍音が聞こえるという御感想を頂きました。特に太い絃を弾くと倍音は聴こえやすいのですが、サワリの調整によってもその特定の倍音を押さえたり出したりすることが出来ます。糸口のサワリのもう少し上の部分に空間が少しあるとキンキン(ヒョンヒョンと言う方が合っているでしょうか)とした高い倍音が出て来ます。これはこれで気持ち良いので、私は割と出るままにしておく事が多いのですが、ちょっと出過ぎると思う時には貝プレートの上部のスネークウッドの部分に軽~くやすりをかけて、隙間を無くし、高い倍音を押さえるようにしています。ただこれは写真で見せてもほとんど判りません。実際に目の前で教えないとどうにも伝わらないのです。象牙の糸口だともっと判りにくいかもしれません。是非お師匠様に教えてもらってください。
それとサワリの調整をする際の残酷な現実として、老眼の方はかなり厳しいです。光にかざしながらやるのですが、細かい隙間がどうしても見えずらくなります。幸い私は普段から眼鏡も必要無く過ごせているので大丈夫なのですが、本を読
む時に老眼鏡が必要な方は、サワリの調整もかなりやりにくいと思います。先ずは柱でも糸口でもその状態が見えないとどうしようもないです。慣れてくると大体音でどういう状態になっているか判るのですが、それでも見えないとまともに調整する事は出来ません。早い方は40代から老眼になってくるようですが、サワリ調整専用のメガネなどを用意する事をお勧めします。こればかりはどうにもなりません。
サワリの音色は、結局その人がどんな音楽をやりたいか、それによって随分違ってきます。材質も勿論ですが、先ずは自分で最適な調整が出来なければいくら材質を変えた所で、求める音は出て来ません。求める音色はそのままその人の音楽です。お稽古事で楽しむのなら、習っている先生と同じで良いと思いますが、時代のセンスが目まぐるしく変化している現代に合って、お稽古事と言えども琵琶樂に対する好みは変化して行くのではないでしょうか。T流などをみていると、流祖と今の門下生はまるで違った歌い方をしています。とても同じ流派とは思えません。これは良い悪いではなく、こういう変化はあらゆる分野で時代の流れと共に当然であるのではないでしょうか。
創造する事を忘れ、技術も根拠も実績も積もうとせず「象牙でなければだめだ」「〇〇ねばならない」「昔は良かった」なんていう、変化を恐れ、過去に寄りかかる薄弱なメンタルで居たら、次世代の琵琶樂は響きません。受け継ぎたいのならどんな分野でも常に「創造」をし続け、「変化」を受け入れる精神が必須です。時代の変化を受け入れないようでは、何事に於いても継続は望めません。

私はすべての琵琶を器楽用にセッティングしているのですが、弾き語りをたまにやる時も塩高モデルの大型琵琶でやりますので、歌う「間」や声量も随分と変えています。声を聴かせる事以上に琵琶を聴かせるのが私のスタイルなので、私の琵琶のセッティングは歌う人に取っては参考にはならないと思いますが、人それぞれの琵琶の音色がもっと世に溢れるのが理想ですね。それぞれのスタイルで魅力ある琵琶の音をどんどん響かせて欲しいですね。ちなみに私は歌に関して、歌い手と弾き手を分ける形でこれからどんどん作品を創って行こうと思ってます。
様々な琵琶の音が響き渡る世の中になって欲しいものです。




