連日の猛暑ですね。体調を崩している方も多いのではないでしょうか。充分に気を付けてください。私はこの所は演奏も週に1度、多くても2回程度ですので、のんびり部屋の中に居る事が多いのですが、この暑さではとても琵琶を担いで飛び回るなんてことは出来ませんね。

今年に入ってから舞台では、ちょっと今迄苦手と思っていた曲や新作などをあえてやっているのですが、曲を見直したり、推敲する機会にもなって良い刺激をもらってます。
曲は家の中で練習している内は判らないのですが、一度舞台にかけてみると、作品の質や持っているエネルギーがダイレクトに判り、その曲を演奏する自分の立ち位置みたいなものも強く感じさせてくれます。不思議なもんです。リスナーと対峙しないと曲の命というものは輝かないのでしょうね。そしてその曲の持っているエネルギーを引き出すためには、その曲に合った技術が必要という事を初演の時などはいつも感じます。だから新作を作ったらそれに合う技術をどんどんプラスして行かないといけないのです。ここ最近は、あまり演奏しない曲を演奏しているせいか、そんなことを改めて感じるようになってきました。いわゆる身体に覚えさせる的な練習を積むことは確かに大事なのですが、ある程度技が出来るようになった時が一番危険です。
それは自分の得て来た肉体的な反応と、覚えて来た知識の奴隷になるからです。新たな作品を舞台にかけるには、今迄の延長線上には無い発想の柔軟さがないと、これまで引いたレールの上から抜け出せません。「初心」とはよく言われることですが、これまでの自分を断ち切って、いつでも新たな自分に成る覚悟を忘れるなという事です。「初」の左側の偏は衣の意味。右側は刀。衣服を作る時には、先ずどんなに美しい反物でもそこに刃を入れ、反物を切らないと衣服になりません。つまり何かを創り出す時に、刃を入れる覚悟を持てという事です。
今迄得て来たものの範疇からでしか発想出来ないと、知らない内に時代も社会もリスナーも関係無いただのオタク状態となり、結局「お見事」な芸にしかなりません。芸術は常に予定調和の真逆に存在してこそ芸術です。
ちょっと視点を変えてみると、いわゆる「練習」には大きな危険が宿っているのです。「一生懸命やりました。課題はすべてこなしました」という方は単なる技芸者であって芸術家ではありません。優れた指導者は生徒のそんな部分を見抜いて、良い方向に導いて行く事でしょう。だからどんな師に就くかが大切なのです。また生徒もそういう感性と器を持った人なら、先生の言っている意味は充分に理解できるでしょう。練習はその質を問われるし、練習の段階でその人の芸術家としての器が試されるのです。琵琶の世界にもそんな良き道を示してくれるお師匠様がいるといいですね。
音楽活動も飛び回っている事に満足してしまう人が多いですが、練習でも何も考えずにただやったという事に満足して、多少の技術が出来るようになった事で満足してしまう事が多いのです。そしてそういうものを「お稽古事」というのです。

そんな事を日々考えながら色々と試すことが出来るのも、それを実践し試すことが出来る現場があるからと言っても過言ではないと思います。毎月の琵琶樂人倶楽部では毎回やりたい事を何でもやっているんですが、演奏・選曲だけでなく、どんなゲストを招くのかという事も含めて会の運営全体で、毎月毎回がある意味実験なのです。上手く行った時もあれば失敗したなと思う事も多々あります。言い換えると、失敗した姿もリスナーに見てもらえるという事です。これはとても大事なところで、何かを成し遂げる事は、どれだけ失敗をしたか、その数が多ければ多い程、成功に近づくのです。皆失敗したくないし、失敗した姿見せたくないですね。しかしそういう部分を曝け出す覚悟の無い人は、いつまで経っても失敗を恐れ、また失敗を隠すようになって、どんどんと委縮してしまいます。
かのスティーブン・ジョブズはあれだけの素晴らしいものを創り出す迄に、とんでもない失敗を繰り返しているのです。今から見るとよくまあこんなものを製品として売り出したなと、思えるようなものを出して、会社も大損害を被っています。現在の日本の会社はどうでしょうか。イノベーションなどと言いながら、形だけセミナーなど開いても、結局大きな失敗はなるべくしないようにしながら、イノベーションしている姿勢は見せておこうとして、体裁だけの部門を作り、いつまで経っても浅い経験しか積まず、目の前をやり過ごしているのではないでしょうか。
私にとって琵琶樂人倶楽部は、その経験が全てが糧となり、舞台へと繋がって行く土台のような場所なのです。もう16年近くそんな事をさせてもらっている事に感謝しかないですね。

琵琶人を見ていると、キチンとしなくてはいけないと強く思い込んでいる人が多過ぎるように思います。立派で良い所だけを見せようとするメンタルでは何も創り出せないし、いつまで経ってもお稽古事から抜け出せません。
もう引退してしまった先輩に、師匠とそっくり瓜二つに演奏する方がいました。部分を聴くと見分けがつかない程の演奏でしたが、とてもまじめて几帳面な性格の方でしたので、表面の形が似てい
るだけに、かえって鶴田遷都は真逆の、神経質な迄に線の細い姿が見えて来るようでした。それがその人の音楽という事なのでしょうが、ベテランという年になっても何とも囚われている風にしか私には見えませんでした。
先日、津村禮次郎先生から、毎回を真剣勝負と思って舞台に臨むという、大変貴重なお話を聞かせてもらいました。しかし真剣=完璧としてしまうと、形ばかりが整って、中身の無いものになってしまいます。形を整える事に終始するのはアマチュアです。間違えないようにきちんとする事は真剣に取り組む事ではありません。そこが判らない人が多いのではないでしょうか。
それに真剣勝負をする舞台が週に何度もあったら、さすがにこの身も心ももちません。真剣勝負を挑むところを見極めてスケジュールも組んで、自分のペースを作って行けるセルフマネージメント能力がないと結局続けて行く事は出来ません。これが広く自分の周りを見渡すことが出来る器というものかもしれません。続けられないという事は、時間をかけて深めて行く事も出来ないという事でもあります。全てに100%というのはただの素人の浅はかな考えでしかありません。それが判らない人は生業として行く事は出来ないのです。何事にも弾力がなのです。
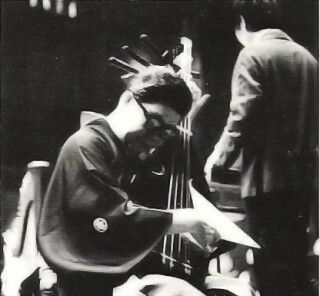 ノヴェンバーステップス初演時の鶴田錦史
ノヴェンバーステップス初演時の鶴田錦史
若き頃に少しばかり就いた先生は「〇〇流は絶対に間違えてはいけないのだ」と言っていましたが、間違えないように完璧に演奏しようとするあまり、技芸だけが聞こえるだけになってしまったら、それはもう音楽ではありません。お稽古事です。
鶴田錦史は、その時々で節を変えて語っていたと聞いていますし、「エクリプス」では尺八の横山勝也との丁々発止のアドリブが過ぎて、作曲者の武満徹から「もうちょっと譜面通りにやってください」と注意されたそうですが、私はその位の幅があって良いと思っています。いい加減にやるという事ではなく、その時その時の自分の姿を曝け出すという覚悟で舞台に立てば良い。完璧に間違えずに、なんて心根では音楽は舞台で演奏できないと私は思っています。
琵琶弾き人生をやっていれば色々な事がありますが、自分に合うちょうど良い弾力を持ち続ける事が出来たからこそ、今までやって来れれたのかなと思っています。
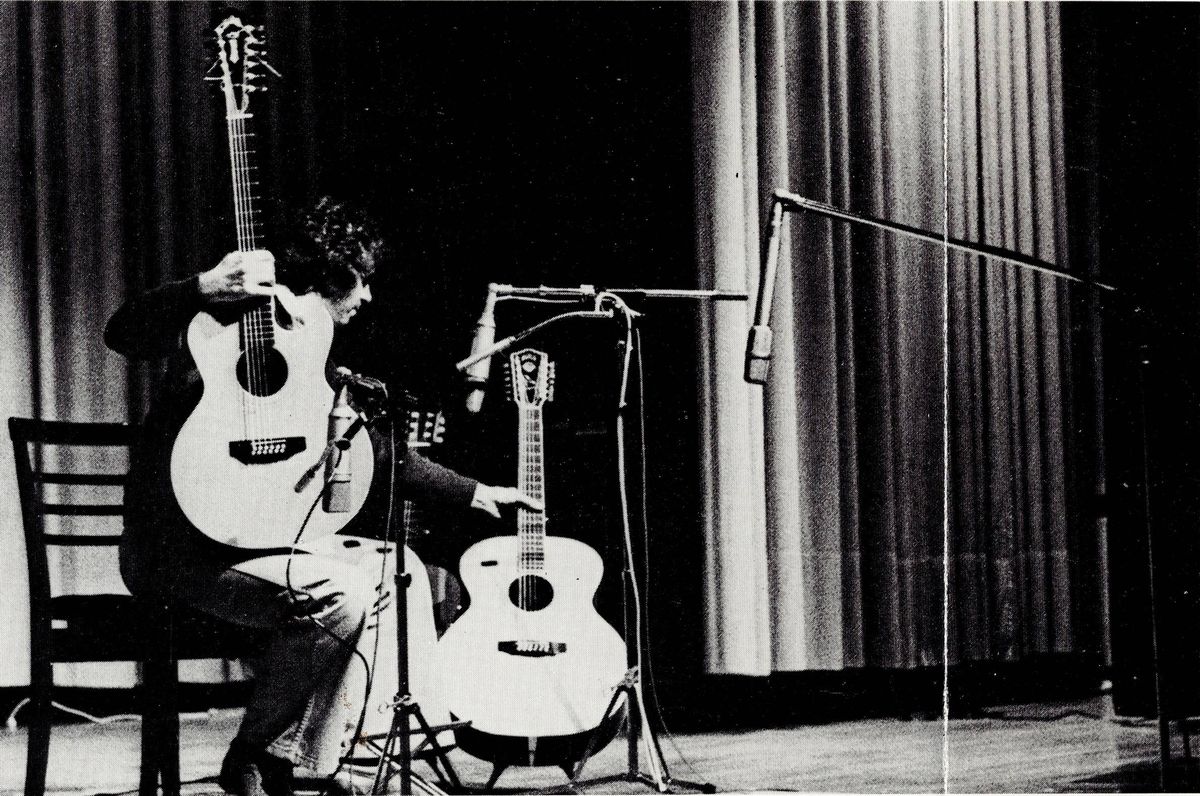
Ralphタウナー「Solo Comcert」アルバムジャケットより
先日の琵琶樂人倶楽部では宮沢賢治の「龍と詩人」をパフォーマーの中村明日香さんとやりました。まだ実験段階ではありましたが、多くの経験を得る事が出来ました。私が琵琶パートの参考にしたのはラルフ・タウナーの「SOLO CONCERT」というライブアルバムです。1979年にECMからリリースされたこのライブアルバムは、既成のジャズやクラシックに寄りかからずに、自分の音楽を追求した若きラルフ・タウナーの感性とエネルギーが迸っているギターミュージックの傑作です。私はこのアルバムを20歳の頃聴いて本当に感激し、この作品が自分の作曲の根底にあると思っています。今でも何度も聞き返しているのですが、今回また聴いてみたら「龍と詩人」の作品に通じるアイデアを感じる事が出来たのです。是非ともこんな作品を遺して行きたいですね。

そんな事を思いながら、もう琵琶を生業として30年近い年月を過ごすことが出来ているというのは本当に幸せな事です。これからも同じように「もう少しで俺の世界が出来上がる」なんて喚きながらやり続けている事でしょう。そしてこうして続けられた方こそ、色々考え、様々な失敗も経験し、深まって行くのです。止めてしまったらそこで終わってしまいます。こんな時間を通して、私は自分のスタイルを作ってきたのであり、今、作品も色々と出来上がって、世に遺すことが出来つつあり嬉しく思っています。「壇ノ浦」を如何に上手に演奏しても、私には空しいだけですからね。
私は失敗をしたり、勘違いをしたりしながら行きつ戻りつしながら続けて来ました。そんな行ったり来たりする事を舞台でさせてもらえて来たからこそ、今迄こうしてやって来れたのだと思います。琵琶樂人倶楽部はそういう意味では、私の土台となってきた場なのです。
年齢や時代と共に活動の在り方は変わって行きます。しかしだからといって目標は変わらない。年齢を重ねる程に納得の行く音楽を創り、演奏し、遺して行きたいですね。



