秋の演奏毎シーズに入りました。例年よりは数がすくないのですが、充実した演奏会を先月辺りからやらせてもらっています。
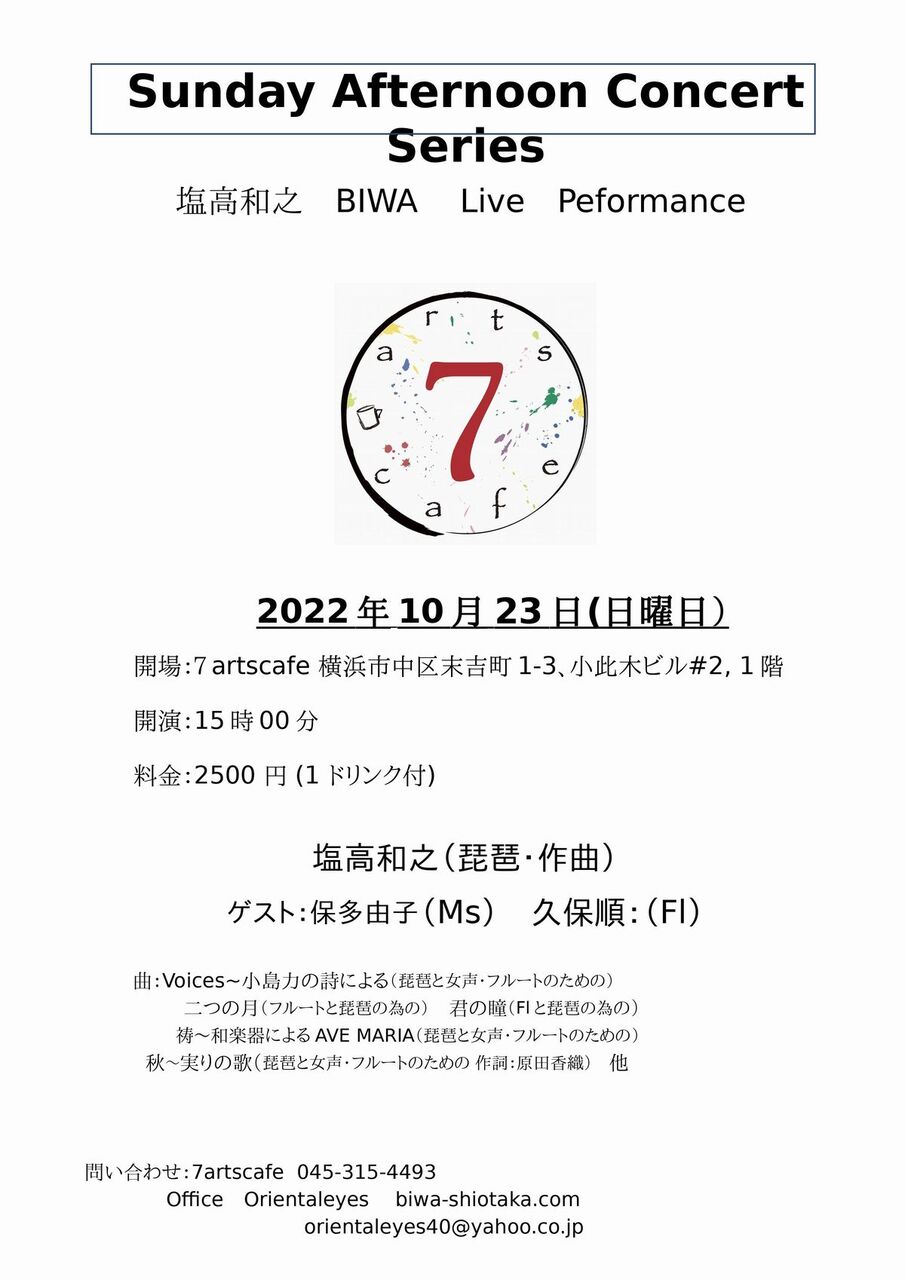
先ずは今週の琵琶樂人倶楽部は、朗読家の櫛部妙有さんと、宮沢賢治の「雁の童子」を上演します。カシュガルを舞台にした幻想的な作品ですので、樂琵琶のオリエンタルな雰囲気ばっちりとはまり良い感じに仕上がっています。
その後は毎年の恒例になっている東洋大学での特別講座。そして上記チラシの横浜7 arts cafeでの第3回となるライブがあります。今回はメゾソプラノの保多由子先生とフルートの久保順さんを迎えてのライブ。先月初演した「Voices」の能管パートをフルートに移し替えての再演です。能管とはまた違ったアプローチで、こちらも良い感じで仕上がってきています。
11月頭には、静岡大学の小二田誠二先生のお声がかりで、静岡の龍華寺(清水)と蓮生寺(藤枝)にて笛の大浦典子さん)と演奏会。
来月の琵琶樂人倶楽部はヴァイオリンの田澤明子先生と、7月に出した11thアルバムの中の曲を中心にしたプログラムで演奏。そして埼玉の武蔵藤沢駅前にある「音降りそそぐ武蔵ホール」で櫛部さんの朗読会に客演。
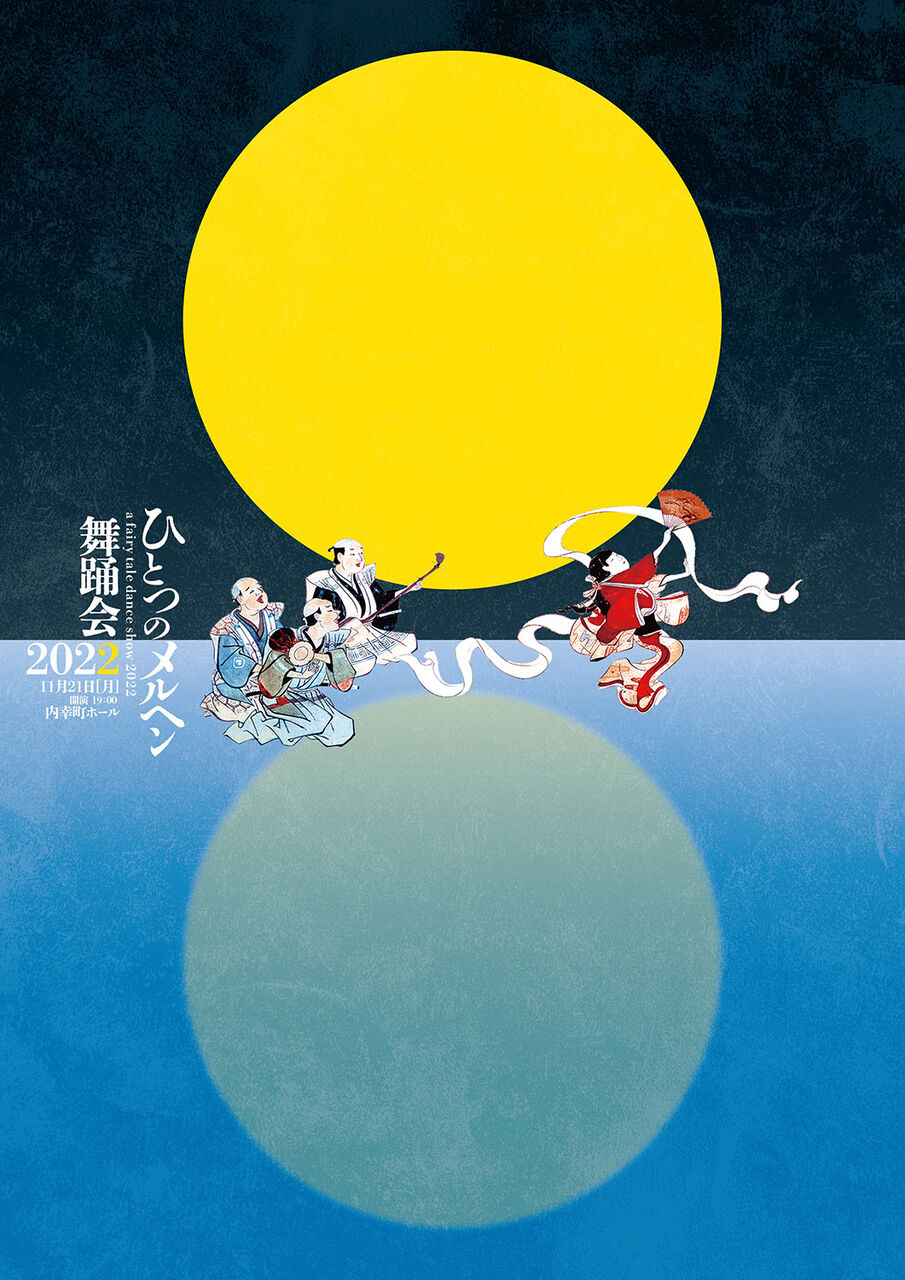 21日には日舞の花柳茂義実さん主催の「ひとつのメルヘン舞踊会2022」(内幸町ホール)にて、中原中也の「湖上」をテーマとした創作舞台で、Tpの金子雄生さんと音楽を担当します。
21日には日舞の花柳茂義実さん主催の「ひとつのメルヘン舞踊会2022」(内幸町ホール)にて、中原中也の「湖上」をテーマとした創作舞台で、Tpの金子雄生さんと音楽を担当します。
加えて今年再開した阿佐ヶ谷ジャズストリートでも、性懲りもなく今年もSKY Trioで遊ばせてもらいます。まあ結構な忙しさですね。いつもの秋が戻ってきた感じですが、やはり私は家で作曲する事と、舞台で演奏する事の両輪が回ってこそはじめて調子が整います。お得意なレパートリーをただやるのではなく、常に新作を引っ提げて舞台に立つ事を、もう25年やっているのですから、当分はこのスタイルも変わらないと思いますね。
相変わらずこんな感じで飛び回っているのですが、私は年を経るごとに「肉体性」というものを色々な場面で感じ・考えるようになりました。自分の肉体が衰えてきている事を感じるからこその感覚なのだと思いますが、現代社会は身体が脳と分離してしまっているような気がするのです。言い方を変えると生々しさが無くなったと言えばよいでしょうか。それは音楽に於いても言える事で、ジャズも今や教室で習うものになって、邦楽と同様、二言目には「○○門下、○○師匠」などという事をミュージシャン達が口にするようになりました。時代は変わりましたね。相変わらずアメリカのジャズメンのコピーのような人がベテランなどと言われ、ロックでさえ、○○ミュージックスクールなんていう所で勉強するというのだから恐れ入ります。コルトレーンやジミヘンが今生きていたら、どう思うのでしょうね。もうジャズもロックも誕生当初の本質を失い、別のものに変質したという事です。それを発展とみるか、もしくは衰退とみるか、それは人によるのでしょうね。
創りたいものを創るのがアーティスト。目の前にある既存の理論や知識は、むしろぶっ壊すものという位の気概を持っている人がアーティストというのではないでしょうか。少なくとも私が聴いて来た音楽家はクラシックでもジャズでも皆そういう人達でした。お上手を目指す時点で既にアーティストという言葉は似合わない。

肉体を失い脳化の進んだ音楽は、原初の呪術性から秩序ある体裁の整った音楽になり、表現する音楽からBGMへとその姿と本質を変えて行きます。洗練とは何事に於いても重要な事ですし、音楽に於いても大事な部分のですが、その洗練の中に、本来持っていただろう魂をどう残し継承して行くかが、アーティストの役目なのです。形に固執せず、時代と共に形を変えながら、その魂を受け継いで行く事が出来れば、幾世代にも渡って継承されて行くでしょう。
反体制や反権力、世の矛盾を暴き出すような所から始まったロックやジャズは今や、綺麗なデジタルリバーブに包まれて、毒気も失い、シャレオツ(古い!)なBGMへと変化を遂げました。お教室で理論やら和音やらを勉強する「お稽古事」となり果てた姿は正に邦楽と重なります。上手も下手も無い、リズムも和音もぶっ壊したような70年代パンクが、音楽表現の最後の砦だったのかもしれません。

私がこれ迄感動した記憶は、感性だけでなく常に肉体の記憶でもありました。初めて握手したエルビン・ジョーンズの手の感触、波多野睦美さんの声を耳より肌が反応した記憶、津村禮次郎先生との「良寛」の舞台で、ラスト8分間で会場が異次元空間に変わってしまったかのような瞬間等々、皆肉体が反応した記憶なのです。
肉体を失った人間は存在できるのでしょうか。今世の中のものが、だんだん目の前のビジュアルや脳内のみで完結するものになって来ていますが、それがどれだけ人間を歪ませ、社会や環境を破壊して行くか、もう一度考えるべき時に来ているように思えてなりません。
私は自分が創り出したものを、舞台の上で演奏するアーティストでありたいです。



