先日近江楽堂にて「ポリゴノーラシンポジウム&コンサート」をやってきました。
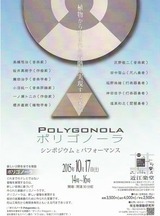
ポリゴノーラとは植物が熟す過程の研究から生まれた新しい楽器のこと。
HPは http://oto-circle.jp/
先ずは灰野敬二さんの以前のパフォーマンスをご覧いただきたい!
円盤又は三角の形をした打楽器で、整数倍音ではない非整数倍音を奏でる新しい楽器です。この楽器を作ったのは広島大学教授の物理学者(専門は植物生理学)桜井直樹先生。スイカが熟す時に、叩いて音を確かめて行くと、その音程がガムランの音程のようだ、という発見から、このポリゴノーラが生まれました。
昨年辺りからこの楽器を世に紹介したいということで、桜井教授の妹である、桜井真樹子さんを通じて私や灰野さんらとやり取りを初めて、私が琵琶研究の薦田先生、尺八の田中君などを紹介し、その他様々な分野の専門家が集まり、今年から研究会を立ち上げ今回の発表に至りました。私はポリゴノーラを使った新作をポリゴノーラ・尺八と共に演奏したのですが、全体を通し、演奏、シンポジウム共に面白い展開となりました。
そして今回は何と言ってもメンバーが凄い!。なかなかこれだけのメンバーは集められません。
櫻井直樹 ポリゴノーラ開発者 物理学者
高橋悠治 音楽家
小沼純一 音楽評論家
薦田治子 音楽学者
一ノ瀬トニカ 作曲家
神田佳子 打楽器奏者
稲野珠緒 打楽器奏者
塩高和之 琵琶奏者
灰野敬二 音楽家
田中黎山 尺八奏者
櫻井真樹子 音楽家
ちょっとびっくりのメンバーですね。高橋悠治さんとは初めてお会いしましたが、ラストのワークショップの時に色々とお話しさせて頂き、嬉しかったです。この他にもスティールパンの製作者 園部良さん、物理学者 小方厚さん、同じく物理学者 秋元秀美さん等がコアメンバーとして、この発表に関わりました。

私は、ポリゴノーラ:灰野敬二さん、尺八:田中黎山君と演奏しました。さすがの灰野さん。なかなかの弾けっぷりで、演奏に潤いと命を与えてくれました。灰野さんとはギター関係の話でも何かと合いますし、これからも色々と組んでいくことになりそうです。また面白くなりそうです。
こうした新しい試みは実に面白い。それに今回は各分野のトップレベルの方々が集った事がレベルをぐんと上げましたね。琵琶奏者としてこういう所に食い込んで行けることが嬉しいですし、琵琶にもまだまだ可能性が十二分にあるということが改めて感じられます。
琵琶楽の研究者である薦田治子先生ともじっくりと話をしましたが、琵琶人はもっともっと色々な因習から解放されるべきだし、正しい歴史も認識すべきです。琵琶というものを素直な目で見る、そんな感性が今こそ必要です。そうしたことがレベルの向上につながり、あらゆる分野に琵琶が浸透して行くのだと思います。弾き語りしかやらない、認めないなどという視野や感性がいかに狭く、世の中からずれてるか、もういい加減に判らなくては。
今後琵琶楽を次世代に継承して行くためには創造が無ければただの保存になってしまいます。創造する力が琵琶樂全体を正しく認識する力になり、次世代に琵琶の響きを伝えることが出来るのです。創造と継承の両輪のバランスこそ今の琵琶楽に問われているのではないでしょうか。

これからやりたいことがいっぱいあります。樂琵琶では敦煌琵琶譜を勉強してみたいし、平曲ももう少し突っ込んでやってみたい。そして薩摩琵琶に於いては、いつも書いているように器楽的な発展が何よりも第一の目的ですが、唄に関しても新たな節付けを考えたいと思っています。平曲は勿論、長唄や謡曲などとても豊かな節があることを思うと、薩摩琵琶の歌の部分ももっと発展して行くのではないかと思っています。ただこれだけの事をやれる時間が私にあるかどうかは判りませんが・・・。
音楽の可能性をあらためて感じた一日でした。



