先日、ヴァイオリニストのグレブ・ニキテンさんの演奏を聴いて来ました。二キティンさんは、現在東京交響楽団のコンサートマスターで、ソリストとしても色々な所で演奏し、指揮者としても活躍している方です。知人からの情報で馳せ参じたのですが、今回はアマチュアオケのゲストという事で、杉並公会堂の大ホールにもかかわらず何と入場料が1000円!アマオケだけの会は何度となくここで聴いていたのですが、一流のプロがソリストで来るというのはまずないので、当日券目当てで、絶対に行列はしない私が並んで入りました。
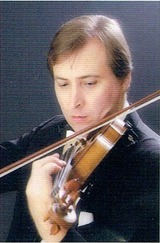 ニキティンさん
ニキティンさん
曲はチャイコフスキーのViコンチェルト。定番ものですが、力みのない余裕溢れる演奏でした。最近はかなり力んで迫力を出そうとする人が多いですが、ニキティンさんはどちらかというとソフト。大きな体から出て来る音色は実に滑らかで、聞いていて不安な部分など全く無く、スラリすらりと音楽が流れ出して行きます。音色も出来上がっていました。
ムター女史を聴きに行った時も思ったのですが、体全体がクラシックになっているとでも言いましょうか、姿に無理が無いのです。ヨーロッパに生まれ育った人間として当たり前といえば当たり前なのですが、これは邦楽でも同じ事で、名手の方々は舞台で実に自然な姿をしています。少しばかり上手に弾けても姿のしっくりこない人は、聞けば聞く程空回りするような演奏をするものです。
これだけ余裕を持って音楽を奏で、歌うヴィオリンはこの所久しぶりでしたので、大変に満足!!オケの方も弦はなかなかまとまっていてスピード感もありました。管はそれなりだったのですが、指揮の中田延亮さんの采配はメリハリがはっきりしていて、音楽が明確に聞こえて来ました。アマチュアにしてはレベルの高いオーケストラだったと思います。ニキティンさんはコンチェルト演奏後何度か拍手に迎えられ出て来て、アンコールで何と今話題のパガニーニの独奏曲を弾いてくれました。あの超絶技巧を難なくさらりと弾きこなす姿は格好良かったです。それも余裕で「こんなことやっているんですよ」とばかりに見せながらにこやかに弾き切る。大したものです。今ではパガニーニの曲もちょっとした演奏家なら誰でも弾きますが、あの余裕はなかなか他では聞けないですね。同じ舞台人として良い勉強になりました。
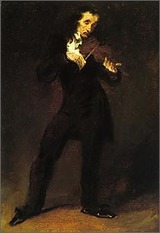
ああやって聞くとヴァイオリンは楽器として本当に完成していますね。実に魅力的です。だからテクニックも洗練され、素晴らしい曲も作られ、更に更に素晴らしい音楽が出来上がって行くのでしょう。技術はあそこまで行って初めて語り出す、そんな風に思いました。琵琶が上手いの下手だのと、そんなレベルとはまるで違います。やはり外に飛びだし、世界を見ることは音楽家として大切ですね。

 幕末から明治にかけて世に出て来た薩摩琵琶は流派というものも無く、個人が勝手に、今で言う所の俺流でやっていました。明治末期に永田錦心が流派というものを打ち立て、薩摩琵琶に洗練をもたらし、美学と様式を明確にして芸術音楽へと導き、全国へと広めていきました。昭和の戦後には鶴田錦史が世界に飛びだし、今度は世界へと広めていきました。私も及ばずながらこの二人の轍を乗り越え、更にその先へと行きたいと思います。その為にももっともっと技術を完成させ、声楽ではなく器楽として広く聞いていただけるよう、更に作曲に演奏に気合を入れたいです。
幕末から明治にかけて世に出て来た薩摩琵琶は流派というものも無く、個人が勝手に、今で言う所の俺流でやっていました。明治末期に永田錦心が流派というものを打ち立て、薩摩琵琶に洗練をもたらし、美学と様式を明確にして芸術音楽へと導き、全国へと広めていきました。昭和の戦後には鶴田錦史が世界に飛びだし、今度は世界へと広めていきました。私も及ばずながらこの二人の轍を乗り越え、更にその先へと行きたいと思います。その為にももっともっと技術を完成させ、声楽ではなく器楽として広く聞いていただけるよう、更に作曲に演奏に気合を入れたいです。
常に大きな世界を見据え、外側へと視野を向けて行く姿勢こそ次の時代を生み出します。小さな村意識の中に居ては何も起こらない!。
ヴァイオリンはうたう。これからは琵琶も楽器が滔々と語り出す時代にしなくては!!

やるべき仕事は山のようにあるのです。



