先日6月11日の水曜日で、毎月開催している琵琶樂人倶楽部も先日で78回目となりました。
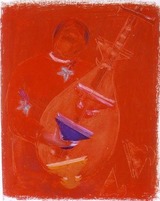
7年に渡り、そろそろ8年目突入も目の前ですが、こうして毎月やって来たというのは、我ながら誇らしく思えます。ライフワークとは正にこの事ですね。
今月のお題は「次代を担う若者達」。なかなか大そうなタイトルです?。今回は筑前の平野多美恵さん、錦心流の佐々木史加さん、薩摩五弦の青山藍子さんに演奏してもらいました。皆さんちょっと緊張気味でしたが、琵琶をやって行きたいという気持ちがひしひしと伝わる演奏でした。

音楽は上手を目指していたら良いものは出来ません。どこまで行っても、表現すべきものが自分の中にあって、初めて音楽と成るのです。上手を求めているのはいわゆるお稽古事。「何を表現したいか」という問いかけを常に持てないようでは音楽家には成れません。皆さんぜひ音楽家として成長して頂きたいと思います。
邦楽では禅の修行のように、先ずは何も考えずに体に覚えさせる、というようなことを言う人も多いですが、何かを習得するためには、研ぎ澄まされた鋭い感性と、思考が必要だという事を忘れてはいけません。ただ言われるがままにやっていても、多少教わったことが流暢に弾けるようになる程度です。確かに思考する事を止めるというのは、自分の頭という小さな器を超える事にもつながると思いますので、大いに有効でしょう。とても大切な事だと思います。しかし考える事、感じる事が出来ない人は何時まで経っても上達しない。上達する人は、色々なものを見て感じる感性が鋭いのです。先生に一つ指摘されら、それに関連する沢山の事にまで思考が及ぶ。自然にそう思える。そういう人が上達するのです。
技というのは筋肉をいくら鍛えても、習得は出来ません。どうしたらその技を出来るようになるか、何を目的として、その技を必要としているか、そういう感性と思考が育たなければなければ、身に付かないのです。感性や思考が出来て来ると、どう筋肉を動かせば、どういう音になるか自ずから見えてきます。だから達人と呼ばれる人の姿は美しいのです。

古典と言われる歴史のあるものでは、様式美という事が良く言われますが、日本の歴史や宗教、過去の芸能、和歌etc.あらゆるものがあって初めて、様式美というものが出来上がり、また身に付いてくるのです。何か一つの上っ面をなぞっただけでは何も身に付かないという事は、まともに考え、感じる力のある人には誰にでも判る事です。茶道やら能やら、色んな習い事をするのは良い事ですが、それら色々なものが文化として自分の中で繋がっていないと、ただの知識で終わってしまいます。それでは表面を装っただけで身に付かない。知識も素養も教養も必要ですが、最後は感性の問題なのです。
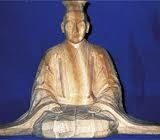 世阿弥も、永田錦心も、宮城道雄も、彼らの思い描く世界を具現化したからこそ、彼らの音楽は未だもって称えられるのであって、上手だとかそんなことではないのです。独自の感性から表現された世界が素晴らしいのです。他にはあり得ないその世界が魅力的なのです。だから我々はそうした先人の感性をこそ勉強しなければならないのです。学ぶべきは形ではない。表に出て来た作品も勿論素晴らしいですが、表面を真似したところで、その作品を生み出した感性を学ばなければ、先人たちの創造性は何も受け継ぐことが出来ないのではないでしょうか。
世阿弥も、永田錦心も、宮城道雄も、彼らの思い描く世界を具現化したからこそ、彼らの音楽は未だもって称えられるのであって、上手だとかそんなことではないのです。独自の感性から表現された世界が素晴らしいのです。他にはあり得ないその世界が魅力的なのです。だから我々はそうした先人の感性をこそ勉強しなければならないのです。学ぶべきは形ではない。表に出て来た作品も勿論素晴らしいですが、表面を真似したところで、その作品を生み出した感性を学ばなければ、先人たちの創造性は何も受け継ぐことが出来ないのではないでしょうか。
勿論、新たな感性で今までに無い世界を創って行くというのは並大抵ではないので、凡人には到底出来るものではないとも思います。しかしだからといって創造という行為を諦めたら、どんどん衰退して行くしかない。たとえ何もできなくとも、創造性を持って取組んで行く事をしなくなったら、もう音楽としては成立しないのです。
また優等生的惰性程やっかいなものもありません。多少お稽古を重ね上手になって自分ではキャリアを積んでいるように錯覚し、大概のものは上手に弾けても自分が何をやるべきか一向に見えていない。演奏する事で充実感に浸りきって、創造という音楽家としての姿勢を忘れてしまう。中には師匠やら先生と呼ばれて、すっかりプロ気取りで浮かれている人も見かけます。
音楽は技芸ではないのです。上手だ、お見事だというのはあくまでお稽古事や趣味の世界。世間でいう音楽とは創造の世界です。ここを勘違いしていたからこそ、邦楽は衰退したのではないでしょうか。創造性と感性を育てなければ!!



先日演奏してくれた3人が今後に対しどんなヴィジョンを持っているのか判りませんが、それぞれのやり方、それぞれの道があると思います。お稽古事で楽しみたいというのも、勿論結構だと思います。私からはあれこれ言うつもりは一切ありません。ただそれぞれが思う魅力ある琵琶楽に、これからも関わって行って欲いな、と彼女たちの演奏を聞きながら思いました。
自分のやり方で、ぜひとも次代を担って行っていただきたいと思います。旺盛なる御精進を!!



