昨日、地元のルーテルむさしの教会で行われた、イースターコンサートに行ってきました。

今回はオーボエ、ソプラノをゲストに迎え、バッハを中心にヴィヴァルディやモーツァルト、ヘンデルなど後期バロックの音楽をたっぷり聞かせてもらいました。
演奏はどれもなかなかのものでしたが、声楽好きとしては歌の曲が何と言ってもぐっときました。バッハのクリスマスオラトリオやモーツァルトの「アレルヤ」
などは本当に素晴らしかった。何と言えばよいのか、とにかくケレンが無いのです。正に「愛を語り、届ける」という感じで、変な自己顕示欲が無くて、音楽が
素直に満ちて来る。宗教曲ですから当たり前といえば当たり前なのですが、邦楽にはあまり感じない雰囲気ですね。
 昨年の3,11追悼集会にて
昨年の3,11追悼集会にて
この武蔵野教会は、キャパが100人ちょっと程ですので、音楽を聴くにはちょうど良い大きさです。声も楽器の音もそのままの音がしっかりと届くのです。特に響きが抜群という訳ではないのですが、とてもナチュラルな感じが気に入っています。昨年より、3,11のイベントやこのイースターコンサートなど、武蔵野教会には何かと縁が出来て、身近な場所になりました。お寺は私にとってどこか修行の場という感じが常にあるのですが、教会はいつでもどうぞ、という迎え入れる雰囲気があって何だかほっこりします。お寺もそんな所がもっと増えて行くといいですね。

仏教が根底にある邦楽は多分に哲学的な要素が強く、愛より先に哲学が来る感じがします。だからどうしてもどこか威圧的な感も否めません。私はそういう凛とした感じの音楽は好きなのですが、美なるものに身を任せ、殉じて至福の時を迎えるような、そんな曲があっても良いと思います。仏教でも「慈愛」や「はからい」というものは重要な要素だと思うので、少なくとも「哀れ」や「悲しい」というような、喜怒哀楽という人間感情の部分で語るようなものだけでなく、もっと大きな概念や視野を根底とした新しい邦楽も積極的に作って行くべきだと思います。
芸術はその先に何を表現するか、そこを問われています。合戦ものや人情ものも結構ですが、目先の楽しさを提供するエンタテイメントで終わるのはあまりにもったいない。琵琶のあの深い音色をもってすれば、日常を超えたもっともっと深遠な世界を表現できると私は思っています。
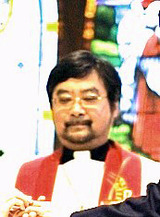 大柴牧師 武蔵野教会HPより
大柴牧師 武蔵野教会HPより
そしてこの武蔵野教会で、いつも楽しみなのは大柴牧師のお話です。何故かこの方の話は私にす~と入ってくる。同郷という事もあるのですが、こういうのを波長が合うというのでしょうか・・・。聴くだけで浄化されます。今回はイースター(復活祭)ですから、それにちなんだお話として、「死は終わりではない」という事を話してくれました。沁みましたね~~。
現代人は、命と言うと有機的・生物的な命という事ばかりを考えてしまいますが、私は、よくここでも書いているように音楽も芸術も命だと思いますし、日本がこれまで辿ってきた歴史も命だと思うのです。だからこそ上っ面をお稽古しただけの邦楽には納得が出来ないのです。
また受け継ぐ過程に於いて、形を変えながら受け継ぐのは当たり前なのではないでしょうか。技を真似た所で、それは単なる保存。むしろ技は常に新しく作るべきなのだと思います。世間では何かというとDNAなどとよくいいます。確かに血筋も大事だと思うのですが、いくら血の繋がった親子でも志や想いを継がない限り、稼業でも家風でも継承はありえない。むしろ受け継ぐべきはその志や想いの方だと思います。形だけ真似ても意味は無い。
私が良く弾く「啄木」は日本にもたらされてからもう1200年経ちます。 作曲されたのはいったい何時なんだろう??と弾く度に思いますが、最初に日本で弾いた藤原貞敏の演奏もどんな風だったかは今となっては解りません。しかしそれは変遷を経ながらも、受け継ぎたいという想いを持った人がどの時代にも居たからこそ、ここまで来たのです。権威あるものとして形だけの継承だったら、とうに消えていたでしょう。伝承者はきっとこの曲に何かしらのロマンを持って伝えたのだと思います。私もこの曲には一つのロマンというか、風景のようなものを感じています。この風景がとても素晴らしい。他には無い魅力に溢れています。これこそが、私が「啄木」をやりたいと思う理由なのです。
作曲されたのはいったい何時なんだろう??と弾く度に思いますが、最初に日本で弾いた藤原貞敏の演奏もどんな風だったかは今となっては解りません。しかしそれは変遷を経ながらも、受け継ぎたいという想いを持った人がどの時代にも居たからこそ、ここまで来たのです。権威あるものとして形だけの継承だったら、とうに消えていたでしょう。伝承者はきっとこの曲に何かしらのロマンを持って伝えたのだと思います。私もこの曲には一つのロマンというか、風景のようなものを感じています。この風景がとても素晴らしい。他には無い魅力に溢れています。これこそが、私が「啄木」をやりたいと思う理由なのです。
1200年という時間を考えると、今に至るまで演奏スタイルや形は相応の変化もしてきていると思いますが、それで良いのです。私は再現をしている訳ではなく、受け継いでいるのですから・・。一度でもその命の連鎖が途絶えてしまったら、今は存在しない。その長きに渡る命を思うと、頭が下がりますね。
 ルーテル市ヶ谷教会
ルーテル市ヶ谷教会藤原貞敏も永田錦心も、まさかこんな奴がこの平成の世に琵琶を弾いて、世間を周っているとは思わなかったでしょう。縁は異なもの。私には残念ながら神や仏の事は解りませんが、そのはからいの中に生かされているような気がしてならないのです。



