先日、建長寺の応真閣にて催された、版画家の井上員男先生の平家物語展にて演奏してきました。

井上先生の作品は六曲屏風に飾られた12作品で、緻密で且つ壮大なその世界は観る者を虜にするような魅力があります。以前、練馬の光が丘美術館で展示された時も演奏しているのですが、鎌倉という場の持つ力なのでしょうか、大広間いっぱいに展示された姿は、以前とはまた違った迫力に満ちていました。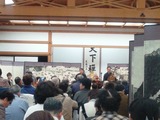
会場は200人を超えるお客様で超満杯。やっぱりこういう所で聴きたいという人が多いのでしょうね。ホールのように響く訳ではありませんでしたが、気持ち良く演奏出来ました。後方からの写真で小さいですが、こんな感じでした。
鎌倉は私にとって何かと縁のある所で、毎年恒例の古民家ミュージアムでのReflectionsの演奏会をはじめ、昨年も魯山人の築いた窯で作陶している河村喜史さんのサロンで演奏したりして、これまで色々な場所で演奏をしてきました。私の弾き語り作品の作詞をしてくれている森田亨先生も鎌倉在住ですので、鎌倉では何かと飲み歩いたり、打ち合わせをしたり、身近な場所でもあります。緑も多く、歴史も深いこういう所はいつ行っても良いですね。ここ数年更に縁が深くなって来ている感じがしています。

琵琶のような古くからある楽器は、おのずと歴史というものを背負っています。薩摩琵琶自体は近現代のものですので、古典という訳ではありませんが、歴史ものを題材としていることもあって、琵琶楽全体という大きなくくりで考えると、ロマンの部分だけは時代を遡って行きます。樂琵琶や平家琵琶は正に平安・鎌倉そのものなので、日本の歴史がそのまま楽器に宿っていると言っても良いかと思います。
そういった歴史を背負う琵琶という楽器に携わっている者として、この平成の時代まで続く歴史を、次代へとつなげて行く事は、おこがましくも何処か使命のようなものを感じます。どうやってやって行くべきか、大いに悩むところでもありますが、少なくとも形をや歴史をなぞるだけでは何か片手落ちのような気がしています。
例えば、古代の遺物は何の目的で使われていたのかも判りません。銅鐸や埴輪が良い例です。神社などでも何の神様を祭ってあるのかも判らなくなって、まるで別物になっている例もあります。つまり過去を過去の形のまま伝えた所で、その意味を伝えなければ、時代によって考え方も価値観も変わってしまうので、物体としての形しか残らないのです。
 蓮如上人坐像
蓮如上人坐像
親鸞聖人の教えも数百年の後には衰退していましたが、蓮如上人が室町時代に、当時の人々に、当時の感性と言葉で、真宗の教えを生き生きと輝くものとして説いたからこそ今があるのです。私達は、過去のものを命あるものとして現代の感性に訴え、伝える事こそがその役割であり、仕事ではないでしょうか。
先ずは歴史をしっかりと正視して、創造性の光を当てなければ、現代にそして次代にも響きません。伝えるべきものに創造性を持って接し、今自分は古典の何を伝えたいのか、その為には現代に於いてどういう表現をすべきなのか、何を変えて行ったらよいのか等々、多くの事を勉強し、考えなくてはなりません。古典をやるという事は、そのものだけを見ていても何も見えてきません。当時の社会、歴史の変遷、宗教いろいろなことが関わっていますので、そういう事もしっかり勉強しなければいけません。また、現代という社会・時代についても明晰な視座を持って見つめていなければ、何も表現できません。かなりの知識と知性、幅広い感性が要求されるのです。
新しいものをどんどんと作り、時代を突き進んで行くのは良いと思いますが、中には何十年しか経っていないものを古典と称して何のはばかりも無く宣伝しているもの等を目にしる事も多々あります。本当に情けなく思います。私にはそうしたものは自己顕示欲の塊のように見えるのです。上っ面の和風文化が今後も残ると思う人は少ないのではないでしょうか。「伝統」というものに少しでも携わる人は深く考えて欲しいものです。

私はいつでも自分で作った作品を演奏します。樂琵琶では古典をそのままやる曲もありますが、それを今、現代に於いて演奏する意味を充分に考え、自分で納得いかなければ、とても舞台にはかえられません。今回演奏した「平敦盛~月下の笛」も現代に於ける敦盛の物語を語るべく、新しく作った作品であると紹介させて頂きましたが、何よりも古典から続くこの日本文化の道程の最先端として、自分の新作を発表出来るという事が私にとっての喜びなのです。私の作品の前には永田錦心が居て、宮城道雄が居て、世阿弥が居て、源博雅も秦河勝も居るのです。先人の残したものが何かしら脈々と伝えられているから、今私が琵琶で新作を発表するという活動をしていられるのです。私自身は、この道程に於いてたとえ取るに足らない末端の存在であっても、このような歴史の大きな流れの中に私の音楽が響いていることは、嬉しいし、ありがたいし、誇りでもあります。
古典は何よりも大事にしなければなりません。同時に古典に寄りかかってもいけません。古典に携わる事で偉くなったように思い込む態度は、奢り以外の何物でもないし、単にそれは勉強が足りないからそうなるのです。やればやるほどに謙虚な姿勢になって行くものではないでしょうか。常に心新たに取り組みたいものですね。
鎌倉の地で、大いに想いを馳せた一日でした。



