
先日は大雪が大変でしたが、やっと春らしい日差しを感じるようになってきました。梅も結構咲いているので、お花見には良い時期になってきましたね。
私は相変わらず逍遥の日々で、ふらりふらりと出歩いていまして、ここ一週間は陶芸家のSさん、朗読家のKさん、人形作家のMさん、タロットのKさん、ジャズ仲間のKさん、Tさん、Oさん等々面白い方々とおしゃべり三昧。色々と面白い事が出来そうな予感がふつふつと湧いてきました。新たな展開成るか??その他いくつかライブにも出かけて、久しぶりにライブハウスの感触を色々と堪能しました。初めて会った方や、尺八のK君、フルートのOさん等久しぶりに会う仲間もいて話に花が咲き、アイデアも出て来ました。このわくわく感が良いですね。
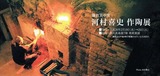
そんな日々の中、今週は横浜高島屋で開催されていた陶芸家の河村喜史さんの個展に行ってきました。河村さんは北鎌倉の其中窯という所で作陶をしている方なのですが、ここはかの魯山人が築いた窯として知れた所。河村さんの祖父喜太郎さんががその窯を受け継ぎ、現在では喜史さんが受け継いでいます。
 河村喜史さん
河村喜史さん
昨年の夏に、窯の横に併設されているアートサロンで私が演奏した折、初対面にも拘らず話が盛り上がってしまったのですが、そもそも河村さんは現代音楽に大変造詣が深く、色々な作曲家ともお付き合いがあるので、私とはばっちり話が合う訳です。今回も作曲家のN先生と呑みながら面白い話を聞いてきたといって、「音の重力」について話をしてくれました。音の出て来る位置、重力について、私はこれまであまり意識が無かったので、お話をしていて大変興味を持ちました。
N先生曰く、「音には重力がある」との事。低音は下から響くし、高音は上から響いてくる。当たり前といえば当たり前なのですが、音の響いてくる位置というものについて、私はこれまであまり考えていませんでした。
ただ一般に民俗音楽は低音域の少ないものが多いと私は常々感じております。日本の邦楽は特にそう思います。明治期に出来上がった薩摩・筑前琵琶などは、以前は皆さん高い調子で歌い、楽器の方も高くチューニングしたこともあって、かなり音域が高い方に集中しているし、また唄い手は高い声が出る事が上手い事とという意識も強かったようですので、総じて高音よりのサウンドでした。
私がどうも近代の邦楽に馴染めなかったのも、低域の少ないあのサウンドが、私に何か引っ掛かりを与えていたという事なのでしょう。それは洋楽を聴いても思う事で、ロックやフォークを聴いても、低域に欠けるものは好きではないです。
 私が敬愛する音色の魔術師 ギタリスト デビッド・ラッセル
私が敬愛する音色の魔術師 ギタリスト デビッド・ラッセル
しかしギターやヴァイオリンなどの独奏曲などは、音域は限られているものの、あまり違和感を感じない。
それは低い音は下から響き、高い音は上から降ってくるという、このバランスが保たれているという事ではないでしょうか。パイプオルガンのように壮大でなくとも、楽器や声そのものが持っている音域を下から上までまんべんなく鳴らしているものには、自ずから高低のバランスが取れ、違和感を感じないのだろうと思います。例えば、叫ぶ声は確かに説得力はありますが、それだけではある音域だけが強調され過ぎて、長く聞いていられない。低くしっとりした語り口は、落ち着いていて癒されるけれども、いつもそうでは熱い想いは伝わらない。結局音域に関しても高低のバランスが取れる事で、音楽としての姿が成り立つのだと思います。
特にその楽器が洗練され、完成されているものならば、持っている音域を充分に鳴らし切れば、魅力ある音や音楽として響いてくるのでしょう。ギターやヴァイオリンのような音域の大して広くない楽器でも、下から響く音、上から降ってくる音が良いバランスで成り立っていれば、そこには調和のとれた世界が現れ、豊かな音楽として魅力ある世界が響いてくるのだと思います。つまり数値的な事よりも、高低のバランスがつりあっている事で、はじめて音の重力というものが明確な違いとなって伝わって来るという事なのだと思います。そしてこれが洗練というものなんだと、話をしながら感じました。

こうした考え方は、多分に西洋的であるとも思います。物事を構造的、構築的に捉え、一つの完成された建築物のように作り上げて行く芸術的思考は、民族音楽の考え方とは大きく違います。しかし現代の我々はもう生まれた時から、自分でも気づかない内にこういった西洋的感性の中で生きている。そんな我々は民俗音楽に対しても近世・近代の日本人とは違う聴き方をしていると言えるでしょう。生活習慣と共に感性が変化するのは当然ですし、日本は150年前からそうした方向で国自体が進んでいるのですから・・・。
私は自分の生きてきた時代を否定するつもりはないので、今のこの感性で邦楽を捉える事の方が自分らしいと思っています。雅楽から平曲、中世の各邦楽など過去の歴史を学ぶのは琵琶奏者として勿論ですが、過去にとらわれることなく、あくまで現代から次代へという視点で邦楽を見つめて行きたい。

私は自分のスペシャルモデルを作り、調弦や弦の太さなどを工夫して使っていますが、それは単に天邪鬼だからというだけでなく、器楽の楽器としてのバランスを求めた結果だったのだと、河村さんと話をしてみて納得してしまいました。
芸術家とのおしゃべりは実に楽しく、且つ視野が広がり、私に新たな発想をもたらしてくれます。「重力」、私
に新たな視点が加わりました。
おしゃべり三昧は止まらないのです。



