また凄い雪になりましたね。雪のお蔭でコンサートが中止になるような影響も色々とあったと思います。私が以前講師をやっていた有明教育芸術短期大学でも、卒業公演が延期になりました。生徒達は残念だったでしょうね。

こんな雪の日は家でCD三昧なのですが、私は時間さえあればコンサートを聞きに行っています。このブログにもその中のほんの少しだけ個人的な感想を書いていますが、アマチュアから世界のトップクラスまで、生音(PA無)でやっているものならジャンル関係なく、とにかく聴きに行きます。今年に入ってから、先日ブログに書いた芸劇での合唱付きオケのコンサートなどの他、舞踊(バレエ・日舞・モダンダンス)、クラシック、邦楽等のコンサートに行ってきました。今月もこれからちょと面白いライブに行く予定です。色々なものを聞くのはとにかく楽しいし、学ぶものも多いですね。一流と言われる方の舞台が何をもって一流と評されるのか、観る程に感じるものがあります。
私は何時も書いている通り、肩書きや受賞歴は全く気にしません。舞台が全てです。今年見た邦楽はいずれも大先生の演奏でしたが、正直歌も演奏の方も大変残念でした。サークルのおさらい会ならともかく、これが邦楽界一流の先生だと言われても・・・。これを最初に聞いた人は邦楽に対してどう思うでしょうね???

演奏は勿論ですが、その質とレベルはやっぱり舞台姿に出ます。やはり心の部分がそのまま姿に出るのだと思いますが、それ以上に一流といわれる人は、一流にしか持ちえない一種の魅力というか狂気(といったら言い過ぎか)みたいなものを皆何処かに持っているのかもしれません。邦楽が今衰退しているのは、その狂気を持っているプロが少なくなったからなのではないでしょうか。
良い曲を書く人が良い人間とは限らない。ベートーヴェンはかなりエキセントリックな性格だったようだし、シェーンベルクも石田一志先生曰く、猜疑心が強く、ちょっとお付き合いしにくいような人物だったようです。チャーリーパー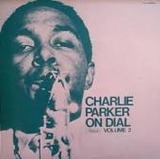 カーも強烈だったようで、色々な逸話が残っていますね。エリッククラプトンも一時はレイシスト発言をするなど、けっして日本のファンのイメージ通りの人物ではない面も持っているようです。
カーも強烈だったようで、色々な逸話が残っていますね。エリッククラプトンも一時はレイシスト発言をするなど、けっして日本のファンのイメージ通りの人物ではない面も持っているようです。
こういう例を挙げると、びっくりする方もいると思いますが、そういう人達が音楽シーンをリードして行ったことは間違いないのです。
素晴らしい音楽は世間でいう所の「良い人」が作り出す訳ではありません。「良い人」はその時代に於いての分別のある良識人かもしれませんが、発想が時代やその時々での常識を飛び越えられない。つまり「良い人」では時代を超えて支持されるようなものを創造する事は難しいのだと思います。肩書きなども結局そんなもので、小さな世界の評価でしかない。それをいつも看板にしているという事は、「私は小さい世界で生きてます」と宣言しているようなものですね。
音楽が時代を超えて支持される質を持っていれば、語り継がれ歴史にも残って行くのは当たり前の事。創った人が今の時代のセンスから見て良い人かどうかなんて問題ではない。時代を超えても尚輝きを失わない魅力、言い方を変えればある種の狂気があるかどうかではないでしょうか。そういうものを創り出せる人だけが、超一流といわれるのだと思います。

まあ超一流と言わずとも、プロの舞台人は舞台運びも上手いし姿も良いですね。様になるという言葉がありますが、やはり素晴らしい演奏をする人は、お作法という事でなく、それなりの様になります。作り出すものがあって、それが素晴らしいものであってはじめて、それに伴って姿も良くなって行くし、舞台も様になってくるものです。所作や姿は、あくまで身から湧き出るものだと思います。一流になればなるほどに・・・。
どの分野であれ、私は超一流の演奏には常に触れていたいし、私自身も出来るかどうかではなく、そこを目指して行きたい。余計なものに惑わされずにしっかり音楽を聴き、作り、演奏し行きたいのです。



