先日、サイガバレエ団主催による「絃楽器の歴史」と銘打った公演をやってきました。

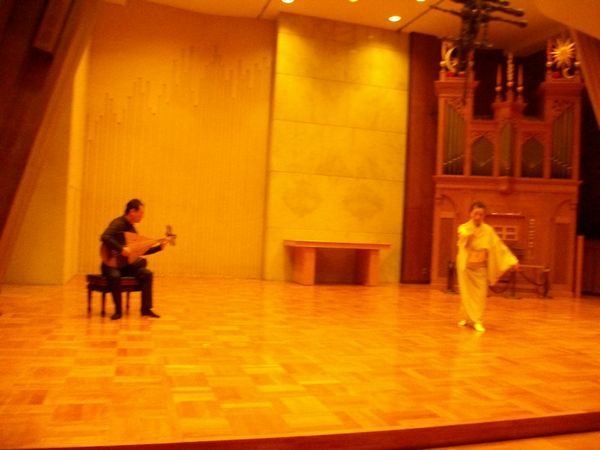 私は絃楽器の歴史のレクチャーと共に、日舞のベテラン 花柳面先生と「久遠」という新作を上演してきました。シルクロードをテーマとした10分程度の作品なのですが、伴奏は樂琵琶のみ。今回も完全に一から作曲し、踊りと共に創り上げました。今までにも日舞とは色々な作品を作ってきましたが、ここにきてようやく納得のいくものが出来た感じがします。
私は絃楽器の歴史のレクチャーと共に、日舞のベテラン 花柳面先生と「久遠」という新作を上演してきました。シルクロードをテーマとした10分程度の作品なのですが、伴奏は樂琵琶のみ。今回も完全に一から作曲し、踊りと共に創り上げました。今までにも日舞とは色々な作品を作ってきましたが、ここにきてようやく納得のいくものが出来た感じがします。
私は自分も興味があるせいか、踊り・ダンスにはとにかく縁があって、毎年踊りの舞台の音楽を担当しています。面先生とも今までに何度も御一緒させていただいていたのですが、大体他のジャンルの踊り手も一緒の事が多く、今回のような1対1でのものは初めてでした。面先生は古典でも大ベテランの踊り手であり、創作ものの作り手としても大変評価されている方なので、御存じの方も多いかと思いますが、70年代から現代音楽の作曲家の作品などを積極的に日舞の世界で取り上げてきた方ですので、「創造とは何か、古典とは何か」等々、いつも良い勉強をさせてもらってます。

古典があってこそ、前衛が生まれるのは当然ですが、古典に胡坐をかいているようなものには命が宿りません。やはり旺盛な創作意欲が無ければ、音楽や舞台は途端に色褪せてしまいます。今衰退している分野は創造性が失せて、創作という事がなされていないからだと思います。また古典に対しても、現代におけるその意味を充分に考え、研究を重ね、明確な意思を持ってやらなければ、「こういうものなんです」と主張しても、もうそれは過去で止まった骨董品や資料としてしか受け取ってもらえません。
どんな形であれ聴衆に魅力を与えられないものは、滅び去るのみです。あふれ出る創造性と古典への眼差し。この二つが高いレベルで存在してこそ、舞台は成り立ってゆくのではないでしょうか。
古典を権威のように宣伝し、肩書きを振りかざすものは論外でしかないのは世間の人は皆判っている。邦楽村の住人だけが幻想に囚われて、周りが見えていないという事に、早く気が付かないといけません。
 よくブログで取り上げる手妻の藤山新太郎先生のように、古典に新しい視点を加え、古典を現代に蘇らせ、それによって手妻という素晴らしい古典芸能を現代に改めて紹介し、ファンを獲得してゆく。これだけの偉業をやってのけるからこそ、藤山先生は第一線のトップを張れるのです。古典を受け継ぐという事は何も形を守ることではなく、その素晴らしさを次世代に伝える事です。そのためにあえて形を変えることも辞さない覚悟が必要なのです。古典だろうが前衛だろうが、旺盛な生命力に満ちた現在進行形のものであることが一番大切なのです!!。
よくブログで取り上げる手妻の藤山新太郎先生のように、古典に新しい視点を加え、古典を現代に蘇らせ、それによって手妻という素晴らしい古典芸能を現代に改めて紹介し、ファンを獲得してゆく。これだけの偉業をやってのけるからこそ、藤山先生は第一線のトップを張れるのです。古典を受け継ぐという事は何も形を守ることではなく、その素晴らしさを次世代に伝える事です。そのためにあえて形を変えることも辞さない覚悟が必要なのです。古典だろうが前衛だろうが、旺盛な生命力に満ちた現在進行形のものであることが一番大切なのです!!。
私は今回のような舞台を、これからもどんどんとやって行きたいし、その為にも日本音楽の古典である能、歌舞伎、雅楽や平曲、そして更に遡ってシルクロードの音楽をどんどんと聴いて、我が身の内に取り入れてゆきたいと思っています。肩書きやお免状掲げて舞台に立つようなことは間違ってもしたくない。
これからも踊りにはどんどん関わって行くだろうと思いますが、器楽としての琵琶楽も更に発展させて、琵琶楽の新時代を作って行きたいですね。
最後にサイガバレエの方々とパチリ。お疲れ様でした。




