舞台「誓い~奇跡のシンガー」の事件は皆さんご存知だと思います。事件そのものについては色々なことが言われておりますし、原作者のブログも大変話題になっていますが、事件そのものよりも、著作権や文化、芸術というものを現代日本人がどう感じているかが、こういう事件から伺えます。
日本では著作権というものが、本当にないがしろにされてきました。はっきり言って日本の常識は世界の非常識と言えるでしょう。世の中がグローバル社会になって行っても、こういう意識だけは変わりませんね。ダンス系の会など以前は無法地帯で、有名な踊り手の方でも、何の罪の意識も無く勝手に音楽を使っていたものです。私のCDも、連絡一つ無く使われていることがよくありました。最近でも時々あります。結局日本人全体に、作曲家や作品に対する尊敬も無ければ、敬意のかけらも無いのです。少しずつ良くなっては来ていますが、まだまだその意識は低いですね。
美術でも音楽でも、ものを生み出すという事がどういう事か、まだまだ認識されていません。社会全体が作品を商品としてしか見ておらず、そこには芸術も文化も無く、ビジネスしかないのです。芸術など特になくてもいいというような意識がまだまだ蔓延っている。残念ながらこれが今の日本の姿です。
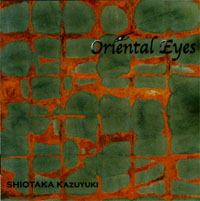

何よりも著作物や作者への敬意があって、そこから展開してゆけば、こういう事件は無いはずです。
余談ですが、私のこの二つのCDは無断使用の頻度が高いみたいです。
今回の事件のような当事者たちは今後、文化芸術に対し敬意を払うようになるだろうか。やり手プロデューサーとしてヒットを飛ばし、業界で息巻いていることしか考えていないような人が、芸術や文化の重要性と素晴らしさに目覚め、敬意と尊敬を持って接し、自らのしてきたことを反省するだろうか???私は無いと思います。
事情も何も熟知している者が勝手に著作物を利用・悪用する事は、れっきとした芸術に対するモラル違反。何らかの重いペナルティーを今後科
すべきでしょう。

ただ、私はがんじがらめに権利意識を持つことは良くないとも思っています。ネット上に写真でも音源でも出していれば、それはもうある程度利用されるのは覚悟の上でないと出すことは出来ません。舞台に立つこと自体がすでに、覚悟が無ければ自分の姿は晒せません。写真はどこでも撮られるし、勝手なこともどんどん書かれ、言われる。舞台人とはそういう存在です。だからプロはそれらを想定して、守るべきものを守る術をしっかり持っていなくてはいけないのです。
 また演奏会に対する意識もほとんど出来ていないのだと思います。おさらい会もライブも、自分主催の演奏会も全部一緒くたで、区別なく演奏しているその意識自体が問題だと思います。
また演奏会に対する意識もほとんど出来ていないのだと思います。おさらい会もライブも、自分主催の演奏会も全部一緒くたで、区別なく演奏しているその意識自体が問題だと思います。
演奏会はあくまで自分の音楽を主張し、披露する場。その創造性や哲学を音楽で具現化するのが目的です。古典作品をやるのであっても、自分の哲学に乗っ取った解釈や、想いや、研究を自分の音楽として聴いていただく場が演奏会です。流派の肩書きをぶら下げて「お上手」を披露するのはあくまでアマチュア世界の事。おさらい会と同じです。プロはそんなことはしない。自分の音楽を聴いていただくのがプロです。だから著作権にも著作隣接権にもしっかり意識を持たないといけないのです。プロの世界とアマチュアのお稽古事を混同してはいけない!。
美術でも文学でも、他の音楽ジャンルでも、こんなことをまだやっているのは邦楽だけです。著作権意識一つとっても、このグローバルな時代に未だこんな状態では、どんどん孤立して滅びるしかないと思うのは私だけでしょうか??。心ある有志、若手がどんどんと出てきて、邦楽界をお稽古事の世界から、芸術音楽を発信する世界へと導いて欲しい。私も微力ながら頑張りたいと思います。

ものです。著作権協会はそれを管理し、その管理を作者が頼んでいる、に過ぎないのです。こういう根本を間違えてはいけない。そして作る側ももっと作者としての矜持を持って生きるべきだと思います。私もとある団体に管理をお願いしていますが、たとえしていなくても、作曲者や作品に対しては、尊敬、敬意をもって接するのが文化国家としての、文化国家に生きる者としての良識というものです。こういう事が定着していない国には成熟も知性も無いに等しい。文化があってこその国家なのです。
それだけ、「創り出す」、「生み出す」という行為は神聖なものだと、私は思っています。皆様はどう思いますか。



