春の日差しが続きますね。花粉も黄砂も暖かさも、まとめてやって来るのが春というものです。私は相変わらずにグシュグシュとやっているのですが、そんな春に吉報が届きました。よくこのブログに登場する音楽学の石田一志先生の著作「シェーンベルクの旅路」が春の芸術選奨・評論の部に選ばれました。石田先生は師匠という訳でもないし、年も離れているのですが、どういう訳か、いつ会っても(呑んでも)話が弾み、大いにシンパシーを感じる方なんです。また私自身もシェーンベルクには大変興味がありますので、何だか妙に嬉しいのです。

私自身はアカデミックな所にはあまり縁が無い人なので、こういう受賞の価値はよく判らない部分もありますが、やはりこうして業績が評価されるというのは嬉しい事だと思います。それに身近な人が評価されるというのもまた気持ちの良いものです。
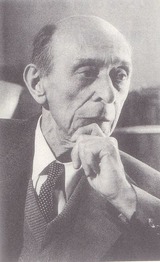 シェーンベルクは石田先生が若い頃からずっと追いかけてきた作曲家です。この本は、出版された時に先生のアトリエで直接頂いてから、一気に読みました。まだ全部は読めていないですが・・・。実に詳細に渡るデータが載っていて、これまでイメージでしかなかったシェーンベルクの実像が浮かび上がってきます。
シェーンベルクは石田先生が若い頃からずっと追いかけてきた作曲家です。この本は、出版された時に先生のアトリエで直接頂いてから、一気に読みました。まだ全部は読めていないですが・・・。実に詳細に渡るデータが載っていて、これまでイメージでしかなかったシェーンベルクの実像が浮かび上がってきます。
またシェーンベルクは明治7年(1874年)の生まれで、ちょうど薩摩琵琶が全国に広まったのと時を同じくしております。思えば現代音楽という新しい分野がここから始まり、日本でも新しい琵琶楽が始まったというのは、色々と考えさせられるものがあります。新しい時代には天才が生まれるのですね。それとも時代が天才を生むのか・・。バルトークやドビュッシー、ラベル、そして永田錦心皆この時期の生まれです。
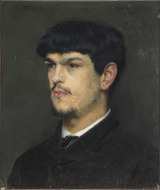

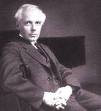
御承知のように、上記の天才たちがクラシックの音楽概念を大きく変え、この新しい時代の息吹が更に受け継がれ、メシアン、ケージ、武満、黛が次の時代を担って行ったと思うと、近代から現代への時代の流れにわくわくしますね。 琵琶では、永田錦心の後、それらを受け継いで水藤錦穣や鶴田錦史が現代の琵琶楽を作って行く過程と重なります。
琵琶では、永田錦心の後、それらを受け継いで水藤錦穣や鶴田錦史が現代の琵琶楽を作って行く過程と重なります。
近代は良くも悪くも、それまでの世界とは一線を引く「新しき時代」。西洋も東洋ももう古典の時代ではないという意識があったのでしょう。そして私たちは(これもよくも悪くも)、その「新しき時代」を土台として生きている。少なくとも薩摩琵琶は曲の題材は古い話でも、音楽性は古典音楽を土台としていない。近現代の音楽です。
![IMG_3405[1]](https://biwa-shiotaka.com/wp-content/uploads/2013/03/9b3206ca.jpg)
シェーンベルクやバルトーク、ドビュッシーに強い興味を持っていた私が薩摩琵琶に関心を持ったのも何かの縁だし、作曲の石井紘美先生との出会いも、石田先生との繋がりも、皆何か見えない糸で繋がっているように思えます。この糸がこれからどんなふうに広がって、どんな音楽が生まれて行くのだろう。そう思うとやはりわくわくします。それには過去をしっかりと勉強分析研究する事がとても大事だと思います。しかし同時に過去に拘り、なぞっているだけでは時代の音楽は生まれない。そこにとどめなく旺盛なまでに溢れ出る創造性が無ければ・・・。
PS:春の芸術選奨ではダンスの森山開次さんも新人賞を取りました。この間ブログに書いたばかりなので、こちらもめでたし!



