少し御無沙汰です。
南相馬に行ってきました。今回はカメラマン 溝江俊介さんのコーディネートによる旅でした。「現地に行って肌で感じ、現地の方々と話をしてみて欲しい」とのことで、ボランティアに行った訳では無く、彼の地をこの目で見て、その土地の人々とたっぷり話をしてきました。特に相馬野馬追太鼓の方々には、練習も見せて頂き、じっくりと杯を交わしながら話をしてきました。
 飯舘村
飯舘村
二本松インターを降り、全村避難の飯舘村を通って行きました。かつては理想郷として紹介されたこともあるこの村には、今や全く人の気配は無く、田んぼも荒れ放題でした。その後、海に近い小高町にも行きましたがこちらもゴーストタウンとなっており、震災の爪後は今もそのままになっていました。
色々な場所に連れて行ってもらい、津波の考えられないような現状も見てきましたが、そういう事を報告するのはまた次の機会にしようと思います。
 野馬追太鼓の練習
野馬追太鼓の練習
 野馬追太鼓のメンバー達
野馬追太鼓のメンバー達
夜になって相馬野馬追太鼓の迫力ある演奏を聴かせて頂き、体にズンズンその鼓動を感じた後は、居酒屋に移動しメンバー達と飲みながら色々な話を聞きました。もう私などには想像もつかないような話が多かったですが、何よりも笑顔で太鼓を叩き、仕事をして、この地で生きて行こうとする彼らの姿からは、多くの示唆を頂きました。
私のように東京に居る人間は、ネットやメディアで飛び交う情報に操られがちで、勝手に見もしないで考えてしまいます。確かに相馬は今、安全とは言い難いかもしれません。他の多くの問題もあります。しかし相馬で生まれ育った彼らは、相馬で生きるのがごく当たり前で、自然な事なのです。震災後帰ってきた若い人も結構居て、原発を横に見ながらも、彼らは相馬の人として普通に暮らしています。
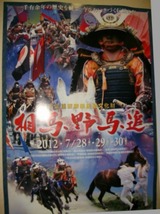
太鼓を叩き、生まれ育った土地に愛情を持ち、熱く地元の祭りの事を語る姿は、日本中の地元を愛する人達と同じだと思いました。私は今年の野馬追祭は行けませんが、是非近いうちに見に行きたいと思います。
震災・津波の爪後は確かに凄まじい。家族を亡くされた話も聞き、未だ放置されている現場も沢山見てきましたが、相馬に彼らが居る限り、相馬にはまた新たな轍が出来て、彼らの作ったその轍が次世代へと受け継がれ、育ってゆくことでしょう。
帰りには小高町から避難している、琵琶の先輩Tさんと会って、話をしてきました。淡々と穏やかに話す中に、しっかりとした視点を持っていて、ここで生きて行こうとする静かな決意を感じました。

私は相変わらず無力です。でも「これからの時代を一緒に生きて行こうぜ!」という方々に出逢えたことは本当に嬉しく思いました。私も彼らと共に、これからの時代を自分の生き方で全うして行こうと思います。
いつか必ず相馬で琵琶のコンサートやるぞ!!



