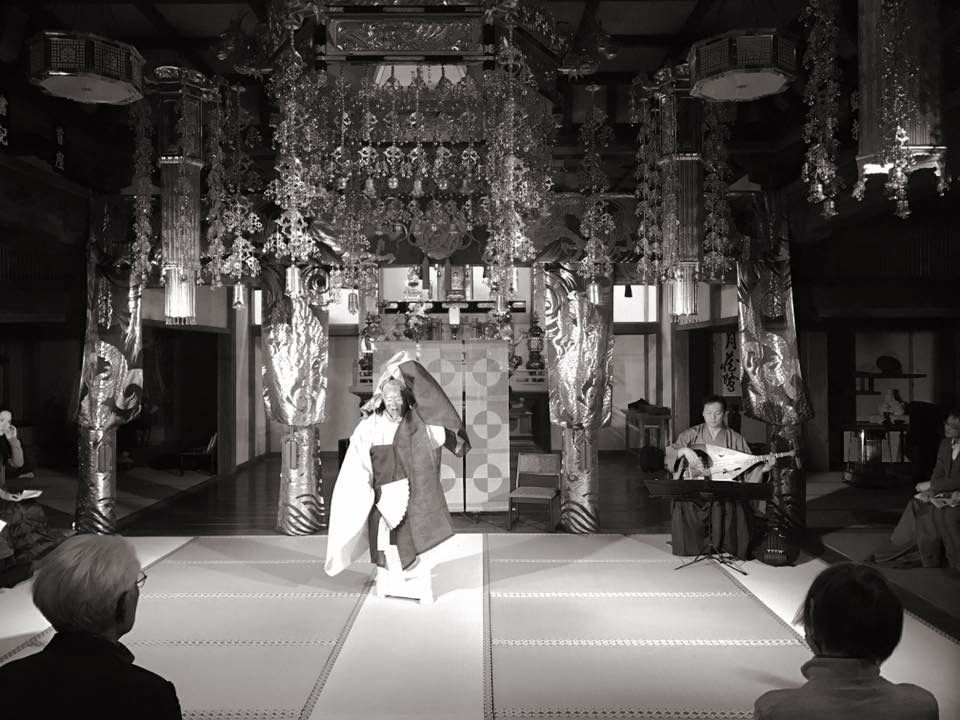梅雨に入り、じめじめとしてきましたね。絹糸にとっては困った季節になりましたが、こういう時にこそ失敗を経験し、学ばなければ!。まあ失敗ばかりというのも何なのですが・・・。
私はこれまで習ってきた先生は、皆タイプがどこか似ているんです。私自身がどんな先生についても同じ学び方をしてきたともいえますが、先生方は皆一様に「自分で何がやりたいのか考える」という課題を与えてくれました。しかしながら一般的には、どうしても一番先に「これが弾き方です。歌い方です。基本です」と教えて、自由に楽器に触らせるという事をしないですね。日本的な教え方とも言えますが、「教える」が「仕込む」と同じ意味になってしまっていて、個性を伸ばすよりも、矯正するように何かの方に押し込めようとするやり方は未だに根強いと思います。以前何度か呼ばれていたインターナショナルスクールでは、生徒に筝でブルースなんか弾かせて楽しんでましたよ。
禅の修行のように「頭で考えずに先ず坐れ」というやり方にも大いに共感する部分があるのですが、こと芸術に関しては、やはり考えながら学ぶという姿勢がないと、型をなぞる事で終わってしまいがちです。これは武道などにも言える事かと思います。
先生と生徒では、年齢、性別、体格、筋力、そして何よりも感性が随分違うと思いますので、先生の思う「正しい」形は必ずしも生徒に合っているとはいえません。これは音楽でも武道でも同じ事で、「これが良い音です」と教えるよりも、自分で「良い音」を見つけるようにさせる位でないと、本当の意味で身については行きません。
先生は「良い音」の価値基準を教えているつもりだと思いますが、それこそ相手が何も知らないと決め付けている上から目線の態度だと思います。それは洗脳でしかないのです。大人なら何かしら自分の価値基準を持っているでしょう。しかし子供にだって、新しい時代の子供の感性があります。その感性を十二分に羽ばたかせてあげるようでなければ、芸術的感性は開きません。それが教育というものではないでしょうか。先生の色に染めるのは洗脳以外の何物でもありません。
教育が洗脳になってしまったら、それはもはや教育ではありません。そこに芸術は無いのです。型を教えるにも、表面の形だけでなく、必ず「何故こうなのか」という中身をしっかりと教えないと、生徒は何の疑問をもたず、型をしっかりとやることで満足し、その中身を考えなくなってしまいます。芸術的思考なしに、得意なものをやって喜んで、どや顔しているだけになってしまいます。そこにはもう音楽はないし、リスナーも聴いてはくれません。学ぶ者は、常に自分で考えながら学ぶ事が何よりも大切なのです。過去だけでなく現代に溢れる多くの音楽・芸術に触れ、自分の感性を磨くことも同時にしていかないと、社会とコミットする事はできません。音楽は社会と共に在ってこそ音楽。だからこそ音に命が宿るのです。社会と関係無いものはただの骨董品でしかありません。
人間は自分の経験を積み重ねて、身を取り巻く多くのものとの関わりを感じ取りながら勉強し、技を習得して行くの至極当たり前です。誰かに「正しい事」を教わったのではありません。
皆さん自転車に初めて乗った時を覚えていますでしょうか。転んだり、補助輪をつけたりしながら自分でバランス感覚を身に付けていった事と思います。最初はお父さんに後ろを持ってもらったりしたことでしょうが、お父さんはその後、自転車の乗り方にあれこれ注文をつけたでしょうか?。楽器だったら、ギターをやっている人は皆判ると思いますが、最初は本をちょっと見たり、弾けるやつの手を見たりしながら、「これがCのコードか」なんて具合に自分で覚えて行ったことでしょう。自然の中で生き延びてきた人間にとって、ものを習得するというのは、自分で考え、経験し、見つけて行くというのが基本です。アドバイスはもらっても、それをどう活用するかを考えなければ、習得は出来ません。あれこれ考えながらやっているその過程こそ経験であり、後々創造性を育む大事な大きな土台となるのです。
神戸芸術文化センターホールにて、語り:伊藤哲哉、コントラバス:水野俊介各氏と
何かの規範の中にのみ居ると、いつしか視野も感性も閉じこもってしまい、勘違いしたプライドさえ生まれてきます。しかも本人は自分がその小さな枠の中に居ることに気づかない。しかし芸術に携わるには、その全く反対の精神を持たなくては創造は出来ません。あらゆる規制、習慣、因習、常識から開放され、自由な精神で生きて、表現してゆこうとするのが芸術家。琵琶でしたら永田錦心、鶴田錦史、両先生のような方こそが芸術家です。この先生達の創った「型」を習うのか、それともその「型」を創り上げた土台となった「精神」を受け継ぐのか、よく考えてみて欲しいですね。どんなジャンルでもそっくりさんは表面が似ているだけで、物まね芸人の域を出ないのです。その類のものを「受け継いでいる」とは誰も評価してはくれません。現代でジミヘンそっくりに弾いたところで評価されるどころか、ただの物真似以上にはならないし音楽家とは評価してくれません。今の琵琶樂の現状を永田先生はどう思うのでしょう・・・・?。
先生に寄りかかり、ティーチャーズペットよろしく先生に気に入られて、優等生ぶっているようでは、芸術から遠く離れた小島に篭っているも同然です。何かを創り出したいのなら、その精神はどんな段階にあっても、どんな状況にあっても、何ものにも囚われない自由な心で、常に多くのことから学ぶ姿勢を持って居なくては!!。「守・破・離」の精神を持って自立して欲しいものです。邦楽・琵琶楽の今後はその精神に掛かっていると言っても過言ではないでしょう。
一方、流派という組織には、計り知れないものがあると私は感じています。勿論まともな流派という事ですが・・。以前邦楽の先輩から「流派とは知性である」と教えられました。確かに流派には、長い年月を経て蓄積され洗練されてきた哲学や、時代の変化に翻弄されながらも生き延びてきた経験があり、所作の一つ一つに意味があります。つまり流派とは大学のような所、と私は考えています。全ての流派がそうだとは思いませんが、古典に対する知識・知性も、旺盛な創作の果てに残されたものの中には、型一つ取ってもそこには深い経験が詰まっているはずです。
だから能のような長い歴史の中で洗練と核心を繰り返して、今尚生きているものを学ぶという事自体はとても重要であり、現代に於いてもしっかりと機能している組織であるならば、その中に教育に関しても充分なシステムが備わっていることと思います。残念ながら薩摩琵琶は個人芸であり、しかも流派というものが出来てまだ100年程度。流派の体を成していません。更には軍国時代の流行音楽という側面もありますので、洗練された型や知性というものは、まだこれから数百年は経たないと現れて来ないでしょう。今の流派に、樂琵琶から始まる千数百年の琵琶樂の歴史を教えられる先生がいるとは、私は思えません。
歴史があり、尚且つ現代にも旺盛な躍動のある「流派」という組織は、学ぶものにとってとても大切な学びの場。薩摩琵琶にも、今後こういう場が成立して行ったら良いですね。
学ぶ身として大事な事は、表面上の型を追わない事。教師もそれを生徒に追わせない事。型を上手にやろうとする浅い心では、その本質はいつまで経っても見えて来ません。型の中に秘められた世界を紐解くのが稽古であり、勉強だと私は思っています。
学ぶとは考える事。私はそう思って実践しています。先ずは先生の事を真似ろ、とばかりに強制して行く教え方・学び方は、芸術に於いては全く的を得て居ないと思います。常に考え、感じ、頭も体もフル回転してこそ学ぶ事が出来ると思っています。
世界一の歴史の長さを誇る日本には、音楽だけをとっても限りないほどに素晴らしいものが沢山ありますし、文学・芸能・歴史・宗教など勉強すべき事は山のようにあるはずです。一生かかっても学びは終わらないでしょう。上手に琵琶が弾けた歌えた、お名前もらったなんて事は、やっと義務教育、いや幼稚園を卒業したという程度。芸術に、音楽に人生を賭けるということは、常に現在進行形で学び、創造して行く人生を選択するという事。お教室で習った事を上手にやって喜んでいるのは、ただのオタク趣味に過ぎないのです。世の中の人はそういう風に見ているのですよ。そんな輩が多いから、いつまで経っても稽古事や河原乞食という目でしか見てもらえないのです。芸術・音楽がもっと社会とコミットし、誇りを持って自国の文化として認識されるには、上手に弾くこと歌うことではなく、次世代に向けて創造してこそではないでしょうか。
私が習ってきた先生方は皆、「貴方は何がやりたいのか」、「それが本当に貴方の音楽なのか」、「やりたい音楽のためには何をやるべきなのか」・・・そういうことを常に問いかけてくれました。また自由にやらせてくれました。だから私は常に、自分で考え、創り、実践した来たのです。そのために学ばなければ行けないことを自分で探し、社会とのかかわりの中で学んできたのです。
若者には、是非多くのことを学んで、新たな日本音楽を創って行って欲しいものです。