何だか急に寒くなりましたね。今週は松本に行くのでコートを着るべきかどうか迷ってます。
近頃はそんなに演奏会は多くはないので、大分時間が取れるようになってきたのですが、さすがに秋は何かと演奏の機会が多く、あちこち飛び回っています。まあその分、色んな芸術家たちと語りあう機会も多くなって楽しい時期でもあるのです。

周りの仲間たちもそれなりの年齢になってきたせいか、最近はよく「力を抜く」という事が話題になります。先日も陶芸家の方と話をしていてそんな話になりました。これは手を抜くわけではなく、余計な力を抜く事であり、また目の前に囚われない事であり、そして作品のレベルを上げる事というです。
これまでの自分の経験や技術などに寄りかかっている人は硬い体をしています。色んなものを守ろうとしているのか、心も体も力で満たし、いわゆる「お見事」をやろうとしている。これではせっかくの技術も経験も生きてきません。ジャズでも邦楽でも80代90代でも驚くような舞台を実現する人が居る一方、ベテランになる程に柔軟性が失われて残念な舞台になっている人をよく見かけます。先日もそんな演奏を聴いて本当に悲しくなりました。
私は元から気合や難行苦行というものとは縁遠い性質で、のんびりとやるのがスタイルなのですが、年を重ねるごとに更に苦行から遠ざかって来ています。先日琵琶樂人倶楽部も16周年を迎えた事もあり、知人達からから「長く続いていますね。色々御苦労もあったでしょう」と会う度に言われるのですが、実はほとんど「御苦労」は無いのです。いつも書いているように集客に関する事はこのブログに書く以外はしていませんし、内容はやりたい事しかやらないので、ストレスも無ければ、嫌な思いをすることも無いし、私としてはただ楽しいので続けているというだけなんです。
孔子様も「これを知るものは、これを好む者に如かず。これを好む者は、これを楽しむ者に如かず」
なんて言ってますが、とにかく頑張っているなどと自分で思っている内は大したことは出来ません。楽しんでいる奴にはかなわないのです。
日本人はこの道一筋で、きつい修行を重ねて耐えて耐え抜いて、辛抱してこそ一人前になると思い込んでいる人があまりに多いですね。未だにスポ根の感覚から抜けれられません。この発想では一つの枠の中に身体も心も閉じ込められ、その小さい閉ざされた枠の中で己の欲望願望も否定して、只管耐えて闘っている状態ですので、ある程度技が出来上がった頃には、視野も感性も体も洗脳されるが如く凝り固まってしまいます。
世界がクリック一つで繋がる時代に、ただ一つの価値観の下で難行苦行をして何かを会得しても、そこに多様な物事や感性を受け入れる事が出来るでしょうか。自分を取り巻く現実がものすごいスピードで変化している現代、その中で大切なのは技術でも小さな業界の評価でもありません。それらは旧来の価値観の中で成立しているもので、世界を相手にする時代には、そこを引きずっていては足かせにしかなりません。自分のヴィジョンを見据え、何が必要で何が足りないかが解る人だけが次の時代を生きて行けるのです。
稽古も修行も、知識や技術を植え付けるのではなく、むしろ自分の中に在るものを見出して行くような方向でやらないと、いつまで経っても自分の歩むべき道は見えません。
努力とは難行苦行ではありません。面白くてしょうがないからやっているだけで、そこに否定は無いのです。根性入れて耐えて辛抱している訳でもないのです。だから一つの事をやっていても、自分を取り巻く面白そうな物事も巻き込むようにどんどん吸収できるし、自分と違う価値観とも触れ合える。そうやって視野も器も育つのです。
難行苦行の果てに「自分はこれだけがんばったんだ」という思いに寄りかかる様になってってしまったら、もうそこから先へは歩みを進める事は出来ないでしょう。それは何故なのか?。それはそこに創る喜びが無く、自分の見えている所だけに居るからです。未来へ視野を向け、新たな世界、次世代へと想いを馳せ、創り出して行く喜びと心が育たないからです。どんなものでもずっと続けている人は最初から何でも嬉々としてやっているんじゃないでしょうか。
面白そうな事は自分の周りに溢れています。そこには可能性も沢山あります。そういうものに視線を向けるには、余裕や余白というものが必要なのです。その余裕を生み出すには、余計な力を抜いて適切な力で動いて行く事が大切。体にこびりついた洗脳されたような価値観や無駄な筋肉、他から与えられたお墨付き、そういうものは過去のものに過ぎません。それらを脱ぎ捨てて、しなやかな心と身体になってのんびり歩いていないと、世の中の動きは勿論の事、樹木や花の溢れる生命感も、風に乗って来た薫りも気が付かず、詩情も沸いて来ません。
何故お見事な自分で居たいのか。そういう自分の内面の闇を素直に見つめ、本当はどうしたいのかじっくり思いを巡らせるのも修行の内です。もっとしなやかになれば色んなものが見え聴こえ、入って来ます。がちがちに凝り固まった心や体で居たら、武道家だったら一瞬でやられてしまいますね。
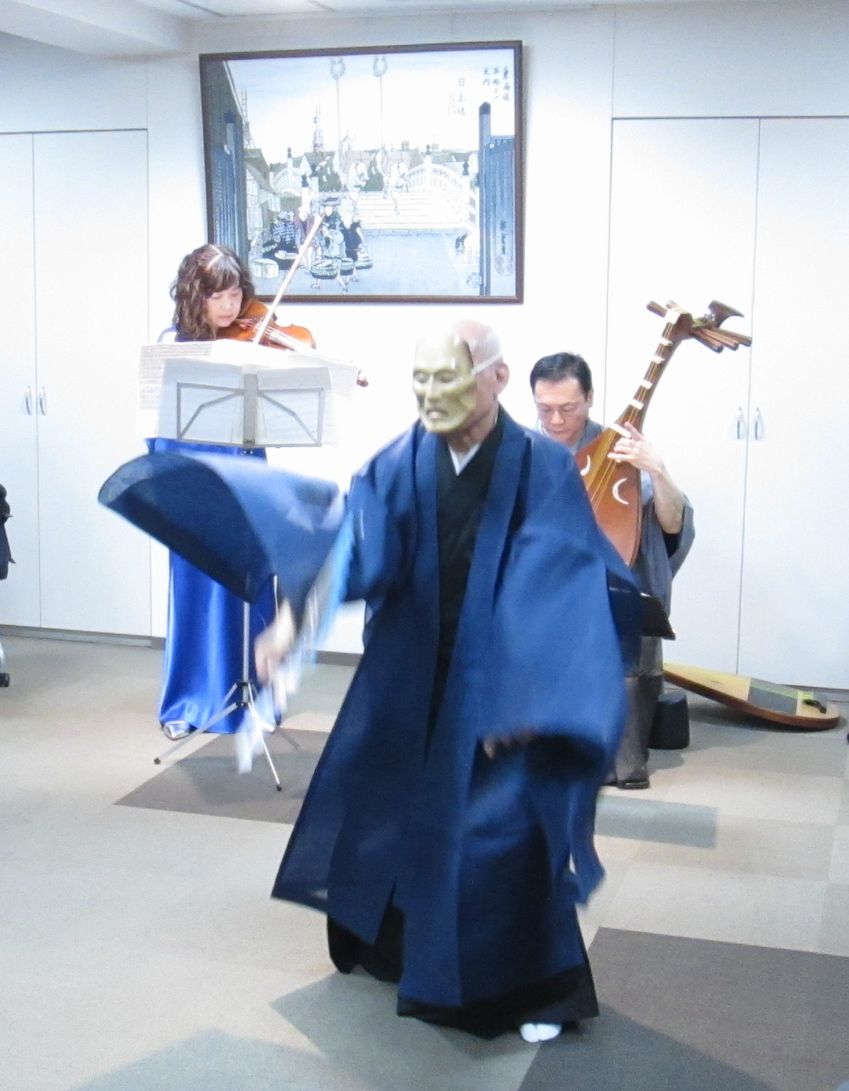
自分は何をやるのか、何故それをやるのか、その発想を生み出す根底の哲学は何なのか。それらを熟考し自分のヴィジョンを自分の内に見出すのが稽古ではないかと私は考えています。そしてそういう心を育てるのが教師なんだとも思っています。歴史上、ヴィジョン無き人間の行動やヴィジョン無き科学技術はそれだけ悲惨なものを生んだか、皆様も解っている事と思います。人間は先へと続く道を見出さないと本当に滅んでしまうのです。
力を抜くという事は、己しか見えない自分よがりの小さな世界から離れ、自分と違う多くのものと触れ合い、受け入れ、世の中全体を見渡し、未来を見つめる心や精神の在り方を養う事であり、最終的には他との調和から愛にまで辿り着く人間の営みそのものなのではないでしょうか。
私の周りにも素晴らしい音楽家芸術家が沢山居ますが、自分なりの活動をしている方は皆、いい具合に力が抜けて、自分のペースで生きていますね。
 かく言う私も以前はシーズンになると、やたらと演奏会が続き、毎月ツアーに出て、それも全て演目が違うというなんて事ばかりで、毎年6月辺りと秋のシーズンは頭も体もパンクしそうな事が何年もずっと続いていて、パワーで押し切っていました。最初から肩書は無いので、つまらないプライドはありませんでしたが、それでもいつしか忙しく動き回っている中で、自分でも判らない内に結構力が入っていて、心も体も固まっていました。そして40代の頃は声に支障をきたすようになっていました。当時色々とお世話になっていたH氏から色々とアドバイスを頂き、肉体的な部分のみならず、いつしか固まっていた心もほぐす事が出来、やっと少しづつ少しづつ力を抜いて行くようになったのです。その辺りから力を抜く事で色んなものを得ることが出来、様々なものが見えるようになり、自分自身ももっと見つめるようになり、やればやる程自分自身になって行くという事を体感して行ったのです。そして自分の中に溢れるものを認識し、誰のものでもない自分の音色と音楽を自然と表すようになったのです。
かく言う私も以前はシーズンになると、やたらと演奏会が続き、毎月ツアーに出て、それも全て演目が違うというなんて事ばかりで、毎年6月辺りと秋のシーズンは頭も体もパンクしそうな事が何年もずっと続いていて、パワーで押し切っていました。最初から肩書は無いので、つまらないプライドはありませんでしたが、それでもいつしか忙しく動き回っている中で、自分でも判らない内に結構力が入っていて、心も体も固まっていました。そして40代の頃は声に支障をきたすようになっていました。当時色々とお世話になっていたH氏から色々とアドバイスを頂き、肉体的な部分のみならず、いつしか固まっていた心もほぐす事が出来、やっと少しづつ少しづつ力を抜いて行くようになったのです。その辺りから力を抜く事で色んなものを得ることが出来、様々なものが見えるようになり、自分自身ももっと見つめるようになり、やればやる程自分自身になって行くという事を体感して行ったのです。そして自分の中に溢れるものを認識し、誰のものでもない自分の音色と音楽を自然と表すようになったのです。
力技で押し切っていた頃もそれなりのパワーで実現していたものもあったと思いますが、そんなものが通用するのはせいぜい20代迄、ぎりぎり30代迄でしょう。それでは何も深まりません。心が自己顕示欲や競争心に囚われていると、姿も目つきもそうなります。40代50代、更には60代になってもそういうものがむき出しになっている人は私にはちょっと醜く見えます。やはり使うべき所に力を使う事が出来て、抜く所はしっかり抜くことが出来、心も体もリラックスしている事は舞台の姿にも、作品にも直結します。
固いものは壊れやすいのです。もっと強いもの固いものに出会うとすぐに壊されてしまう。特に心が固くなると自分と違うものを受け入れられなくなって、視野も感性も失って、結果的に体も壊れてしまいます。自分がやっているものと違うやり方を認めず、未来を想像する事も難しくなってしまったら、良い結果が生まれるでしょうか。判りきっている事なのに、囚われている内は自分の姿が見えません。
今音楽だけでなく、総てのものが世界中との繋がりの中で成り立っています。私のような地味な音楽でさえ、マーケットは既に身内の業界でも日本でもなく「世界」なのです。全世界とつながり、自分の音楽が世界中に流れているという現実を今どれだけの人が認識しているでしょう。思考を止めて、今迄の実績に寄りかかり、ただ形を守っていれば良い、目の前をキチンとして入れば問題ない、気合を入れていれば良いのだ等という硬直し凝り固まった感性は、言い方を変えれば未来を否定して自ら逃避しているのと同じだと私は思います。

先ずは力を抜き、正中線と重心を意識し、本来この体を保つべき力のみで立ってみる。腕や足を筋肉で動かすのではなく骨格や重心を使って動いてみる。そんな風にしていると琵琶を弾く時に撥を握る手に力を入れなくてもしなやかに撥は舞います。逆に力を入れていると撥は舞わない。私は最初に習った高田栄水先生に「撥は蝶が舞うが如くに扱え」とよく言われました。これは単にばちを扱う技術という事だけでなく、その心の在り方をも意味していたんだと今でも感じています。
私は一番自分らしい生き方をしたい。それにはただのオタクのように琵琶だけ弾いてりゃいいという単純なものではありません。音楽もその他の芸術も文学も歴史も、世界との比較文化論も活動を続けて行けば行く程に必要になってきます。しかし「お勉強」をしなくてはいけないという思考では、苦しみや辛抱の感覚から逃れられません。むしろ本を読んだり、新作を書いたり、そんな事をするのが楽しくてしょうがないという位でなくては!!。少なくとも「食うための芸」に陥ったような音楽家にだけは成りたくないし、そんな人生は求めていないのです。
やればやる程に見えてしまうのは技ではなく、その人の器です。力を抜いて、しなやかな心身となって、自分なりの人生を全うしたいですね。



