来月の第140回琵琶樂人倶楽部は、毎年恒例のSPレコードコンサートをやります。今年は「永田錦心とその時代Ⅳ」と題しまして、第一部が永田錦心の特集。第二部は色んなジャンルから、ラッパ録音のものと、マイクロフォンが出来てからの電気録音のものを聴き比べていただくように企画しました。
ご存知のように薩摩琵琶に流派が出来あがり、一般に広まったのは明治の中後期。まだ100年ちょっとしか経っていない若い芸能です。加えて軍国時代とそのまま重なりますので、現代の感性とは相容れないも曲も多々あります。私自身は演奏にあたって、軍国ものや戦の曲などは、定番の「壇ノ浦」「敦盛」以外はずっと避けてきたのですが(それらもかなりオリジナルにしてあります)、今回はあえて軍国時代を象徴するような曲を選び、薩摩琵琶の負の部分とも言える一面をあらためて炙り出して、薩摩琵琶のこれまでの実体を知ってもらおうと思っています。そして今こそ、そういうところから抜け出して、新たなものを次世代に向けた薩摩琵琶のこれからの形を考えてもらいたい、という想いから、こんな企画をしてみました。
永田錦心の時代は、言い換えれば、薩摩琵琶がショウビジネスに乗って行った時代でした。SPレコードが発売され、永田自身もそのニューメディアのお陰で全国にその名と演奏が広まったのですが、今で言えばネット配信で広がったのと同じ事です。
こうして音楽が全国へと広がり、ショウビジネス化して行くと、どうしても世の流れや雰囲気に添わない訳にはいかなくなります。それは単純に売れないからで、ショウビジネスに於いては、売れないものは価値がないものと考えられてしまうからです。今回かける軍国的な曲もそういう中で録音された事と思います。
音楽が広まるのは結構な事ですが、売る事を優先させるようになると、演者もすぐにそれに追随する「売れたい」と思う者が出てきます。今でもはもうショウビジネス=エンタテイメント=音楽という図式が普通となっていますが、それは大正時代辺りから既に琵琶の世界にもあったのです。こうしたセンスが良い悪いは別として、少なくとも表現活動としての音楽とはまた違う、エンタテイメントとしての音楽になって行かざるを得ないのは、近世邦楽を見ても明らかです。
永田錦心がかなりの頻度で琵琶新聞誌上に於いて、琵琶楽の現状を嘆き、檄を飛ばし、芸術音楽として次世代の琵琶楽を創造する新たな才能を待ち望んでいることを何度も書き連ねているのは、表現よりも「売れる」ことを目的として動くようになってしまい、技芸を凝らして、技を聞かせるようになってしまった琵琶楽を大いに憂いでいたからです。
永田錦心は明治という時代に、新たな価値観とセンスを示し、新たなスタイルを創り上げました。正に当時の最先端であり、創造こそが永田の根本だったのです。しかし永田の後に続く者たちは、その精神を継がなかった。永田の示した創造するという精神の根本は忘れられ、次世代の琵琶楽を創り上げる者は永田が組織した中からは出てきませんでした。むしろ組織から追い出された、水藤錦穣やその弟子の鶴田錦史が新たなスタイルを創り上げたのです(しかしそれもそこで止まってしまった)。新たな時代に、新たな感性で、新たな音楽を作り上げるという創造の精神は消え、未だ技芸や肩書きを競いあっているこの現状を、永田錦心はどんな想いで見ているのでしょうか。
キッドアイラックアート」ホールにて、Per:灰野敬二、尺八:田中黎山、琵琶:私
日本は近世邦楽辺りから、いわゆる武家や貴族などのようなスポンサーが居なくなり、自らが稼がなくてはいけない状態となり、近世からは三味線の登場と共に、その担い手も一般庶民になってから、大きな変化が生まれました。
三味線文化圏の音楽や演劇は、それまでの音楽のあり方を根底から覆したのです。名前をころころと変えるのも日本音楽の中では三味線文化圏だけです。この音楽の質そのものの変化は、とてもダイナミックで興味深いところではありますが、とにかく近世以降、現在に至るまで日本型のショウビジネスがずっと続いており、何か主張を持って表現する芸術音楽の方向ではなく、歌舞伎に代表されるように、とにかく売れる、受けるというものがもてはやされ、またそれが実現できる芸人が凄いというエンタテイメントになって行きました。
永田錦心は日本画家でもありましたし、東京の人でしたから、明治になって西洋の芸術を目にすることも多かったことと思います。また西洋音楽のことにも言及している文面を読むと、当時のクラシックの最先端である、ドビュッシー、ラベル、シェーンベルク、バルトークなどを聴いていたのだと思います。少なくとも、あれだけ琵琶楽に対し主張を繰り返しているのですから、それまでの近世以降の日本型の三味線文化圏の芸能ではなく、あくまで表現活動としての芸術音楽を目指したのは間違いないと思われます。
現在、新たな時代の新たな音楽の創造を目指し、自分が表現する音楽を求めている人は、琵琶人では見かけませんね。演歌歌手のバックでTVに出て喜んでいるような人は見かけますが、永田錦心の精神を継いでいるような人は、未だお目にかからないです。まあ人それぞれですから、好きにやれば良いと思いますが、私は永田錦心というパイオニアの示してくれた道を、微力ながらも更に開拓して行きたいです。是非志を同じにする仲間が出て来て欲しいですね。
琵琶楽が次世代へ向けて、魅力ある音楽を奏でてくれる事を願ってやみません。
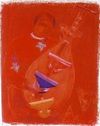
第140回琵琶樂人倶楽部「SPレコードコンサート~永田錦心とその時代Ⅳ」
8月18日(日曜日) 午後6時開演(何時もより早い開演となります。席数が25ほどしかないので、お早めにどうぞ)
料金:1000円(コーヒー付)
お待ちしています。







